日露戦争を題材にしたストラテジーゲームを開発中のStorm Eagleは,ウォーゲーマーの間ではそこそこ知られる,ジム・ローズ氏とノーム・コーガー氏によって設立された開発チームである。日本人としては,その題材だけでも十分興味を惹かれるところではあるが,グラフィックスやシミュレーション部分,オンライン流通に至るまで,さまざまな面で話題性のあるゲームに仕上がりそうだ。今回は,そのローズ氏にコンタクトをとり,いろいろと話を聞いてみた。
■日露戦争の海戦をテーマにした正統派ウォーゲーム
今からおよそ100年前の1904年から1905年にかけて,東洋の小国・日本が北の巨人・帝政ロシアと真っ向から勝負した日露戦争は,日本が列強の一員として認められる最初の国際舞台だったと言える。100年前というと,世界のほとんどがヨーロッパの植民地だった時代。ポーツマス条約によって終戦に持ち込んだ日本は,これを契機に,大陸に向けた領土拡大へとまい進することとなった。
そんな東アジアの近代史が,アメリカでストラテジーゲームとして蘇ろうとしている。まだあまり話題になっていないタイトルだが,その名を「Distant Guns: The Russian-Japanese War at Sea」という,海戦RTSである。
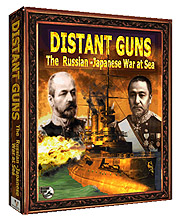
日露戦争を扱った本格的なウォーゲーム「Distant Guns: The Russian-Japanese War at Sea」が,Storm Eagleの処女作。ボードゲームのような地味さが払拭された美しいグラフィックスを誇る作品だ
このゲームを開発するStorm Eagle Studiosの名を,初めて聞いたという人も多いだろう。それもそのはず,Storm Eagleにとって,本作が初めてのリリース作品である。ただし,この開発チームの中核となるのは,Talonsoftの元社長Jim Rose(ジム・ローズ)氏と,SSI時代から“ウォーゲームのモーツァルト”の異名を持つゲームデザイナー,Norm Koger(ノーム・コーガー)氏のご両人。ウォーゲームファンにはよく知られた,ベテラン中のベテラン業界人なのだ。
1995年にローズ氏によって創設されたTalonsoftは,次々とヒット作を生み出した。中でも,1996年の「Battleground: Ardennes」から始まるBattlegroundシリーズは,計8作もリリースされるほどの人気となった。これは,ヘックス(六角形のマス)が並ぶ2D画面のターン制ストラテジーで,Avalon Hillで戦争モノのボードゲームをプロデュースしていたというローズ氏らしい,正統派のウォーゲームだった。
このころコーガー氏は,老舗のSSIで「Age of Rifles」というストラテジーゲームを開発しており,両氏はゲーム市場から見ると,ライバル関係にあったと言える。
当時は各社が躍起になって3Dグラフィックスのゲームを開発しており,コーガー氏自身もゲームエンジンを3度も書き直させられるなどして,ゲームの真の面白さをないがしろにする経営陣には辟易していたらしい。そして自らTalonsoftに企画を持ち込み,新天地で実現したのが,1998年の「The Operational Art of War」だったわけである。
そして2001年春,TalonsoftはGathering of Developers(Take-Two Interactiveの当時のPCゲームブランド)に買収された。これが,Storm Eagle Studiosが誕生するきっかけとなった。
■ウォーゲームが新時代へと突入か?
さて,近日中にリリース予定のDistant Gunsに話を戻そう。本作では,これまでのウォーゲームの地味さを払拭するような,美しいグラフィックスを実現する3Dレンダリングエンジンが開発されている。Storm Eagle Studios独自の開発で,その名もDistant Guns!エンジンだ。

Distant Gunsはグラフィックス,物理シミュレーション,AIなどにも特徴があり,歴史ストラテジーのファンなら押さえておきたいところ
日露戦争という,アメリカには直接的に関係のない出来事を,同社が処女作としてゲーム化することを意外に感じている読者もいるかもしれない。
しかし日露戦争は,史上初めて,装甲巡洋艦や水雷艇などの近代兵器を多用した組織的な海戦が行われるなど,歴史的にも新たな時代の到来を告げる大事件であったのは言うまでもない。20世紀に起こったさまざまな海戦を,Distant Guns!エンジンをコアにしてシリーズ化していくことを狙うStorm Eagleが,1作目にこのテーマを選んだとしても,それほど不思議ではないわけだ。
ゲームでは,1904年2月の仁川沖海戦を皮切りに,同8月の黄海海戦や1905年5月の日本海海戦などを中心にしたさまざまな海の戦場が,100平方kmに及ぶ一つの大きなマップの中で,すべてリアルタイムで描かれることになる。
昼夜や気象も刻々と変化するが,そのディテールとシミュレーションへのこだわりは尋常ではないようだ。
例えば,このゲームには248隻に及ぶ軍艦が登場するが,よく見ると甲板上では,水兵達が忙しそうに走り回っている。これらの軍艦は装甲の厚さや推進力はもちろん,砲の位置から砲弾の命中率,加速力に至るまで,実際のデータをもとに完全シミュレートしており,さらには砲弾や魚雷さえもモデリングしているという凝りようだ。
排煙で視界が悪くなったり,“しけ”で砲座よりも波が高くなって砲撃さえもままならなくなったりと,戦場におけるリアリティもとことん追求されている。
戦列を作って海原を進んでいく艦隊の様子は,実に素晴らしい。インタフェースはそれほど複雑ではなく,それぞれの艦がぶつからないように艦長らに指示を出すことができるし,腕に自信があれば,それぞれの軍艦を直接操作してもいい。もっとも,フォーメーションは重要視されており,一般的なRTSと違って撃沈されたユニットは二度と帰ってこない(再生産できない)ため,プレイヤーのマネージメント能力が問われることになりそうだ。
マルチプレイヤーモードは16人まで対応する予定で,3Dサラウンド対応など細かい部分もしっかりとサポートされている。Distant Gunsシリーズは海戦に特化したウォーゲームとなりそうだが,リリース後には,各シリーズ用の陸戦版アドオンが登場する計画もあるらしい。
■ローズ氏へのメールインタビュー
今回このDistant Guns: The Russian-Japanese War at Seaを開発するStorm Eagle Studiosのジム・ローズ氏へ,メールインタビューを行った。
このゲームの注目すべき点は,日露戦争という題材や,シミュレーションの素晴らしさだけではない。PCゲームの流通や,海賊版に対する保護へのアプローチも,実にユニークだ。そのあたりも聞いてみた。
 Storm Eagle社に導入されたばかりの,128チャンネルのソニー製DMX-R100(通称ベイビー・オックスフォード)で作業するジム・ローズ氏 |
 “ウォーゲームのモーツァルト”の異名も持つノーム・コーガー氏は,なんと空手で黒帯だとか。かなりの日本通のようだ |
Q:
早速ですが,Storm Eagle Studiosと,お二人の自己紹介からお願いします。
A:
私はジム・ローズで,Storm Eagle Studiosの創設者の一人であり,Kapellmeister(指揮者/楽長)という肩書きを持っています。この開発会社は,TalonsoftをTake-Two Interactiveに売却して一度引退した2001年の秋に,ノーム・コーガーと共に興しました。ちなみに,ノームの肩書きもやはり音楽に関係があり,Maestro(偉大な作曲家)です(笑)。
Storm Eagle Studiosは,これまでとはまったく違うコンセプトを胸に抱いて設立した会社です。具体的には,3D環境と歴史ストラテジーを融合し,それでいて,どこか忘れかけていたゲームデザインでの面白さや楽しさを追求してみようと思っています。Distant Gunsシリーズでは,これらすべてをプレイヤーの皆さんにお届けできるはずですよ。
Q:
画面写真を見る限りでは,なかなか性能の良いゲームエンジンのようですね。
A:
数年かけて開発したDistant Guns!用レンダリングエンジンは,3D環境でのバトルフィールドを想定して制作したものです。多くのユニット……つまりこのゲームの場合は軍艦ですが,艦上で動き回る人も含めて多くのユニットを表示できるように最適化し,艦から噴出される黒煙が混じり合ったりという効果もうまく表現できるように工夫しました。
煙というのは,レンダリングサイクルを消費するので負担が大きく,3Dグラフィックスでの表現が難しいものなのです。艦のモデリングも実によく出来ていて,ドイツの船舶専門誌が,なぜかDistant Guns!の特集記事を組んでくれたほどなんですよ。
しかし,グラフィックス以上に見てほしいのが,AIですね。フォーメーションの組み方や,それをさっと分離させるタイミング,そして接敵角度と回頭,攻撃開始タイミングの関係などは,ノームが一番誇りとしている部分のようです。
Q:
シミュレーションやタクティカルな部分を,詳しく教えてください。
A:
ゲームの制作にあたり,この時代の海戦法などはずいぶんと勉強しましたが,やはり興味深かったのは,日露戦争は現代的な海戦が行われた初めての事例だったということです。魚雷や電気制御の砲撃など技術的な進歩があり,それをいかに戦闘に取り入れるかが問われた戦争でした。
艦隊のフォーメーションなどは,これら近代兵器に対する防御側からの戦法だったのであり,このゲームでも重要な戦略の一つになっています。軍艦は1隻,1艦隊,そして全艦隊まで操作することができますが,攻撃や魚雷の回避などに対応して,ユニットをいつ,どのようにプレイヤーが操作するかが,戦場において大きなポイントになるでしょう。
Q:
日本とロシアの双方でプレイできるんですよね?
A:
もちろんです。史実に絡めたゲームプレイとして,日本海軍でプレイする場合は,中国や朝鮮半島にいる陸軍に物資が届くよう,輸送船の安全を確保すべく制海権を握る必要があり,逆にロシア軍であれば,輸送船をできるだけ撃沈しなくてはいけません。海上ルートの掌握が,陸戦に影響するわけですね。長い航海で兵士が疲れきっているロシア軍と,自国の軍港に近くて士気の高い日本軍という違いもあります。
このゲームでは,12の戦場が三つのキャンペーンに分かれて用意されています。ポート・アーサー(旅順港),対馬沖海戦(日本海海戦),黄海,蔚山,済物浦(仁川沖海戦),ノーヴィク号の追跡などですね。ゲームは1年半近くにわたってすべてリアルタイムで行われ,何も戦闘していない時間は,物資補給や艦隊の修復に努めることができますし,用意が整っていれば,時間を早送りして次に進むことができます。
Q:
本作では,独自のオンライン流通を計画しているそうですね。それについて教えてください。
A:
ここ6,7年ほどで,PCゲームは小売店からずいぶんとプレッシャーを受けるようになったと感じています。大きな店舗でも,PCゲームには1列分の陳列棚しかあてがわれていませんし,当然そこには,ビッグタイトルばかりが並んでいる状態ですよね。
販売側に潤沢な資金があれば,派手な広告宣伝で商品寿命を延ばすこともできるでしょうが,それもせいぜい,数週間のことに過ぎません。いずれ販売数は急落し,店舗からは吐き出されてしまう運命にあるわけです。「DOOM」のような人気作品でもなければ,マスマーケットへのアピールが低いとみなされ,長い間陳列棚に居座ることはできません。
しかし,今ではブロードバンド回線が広く普及しており,制作したコンテンツを,仲介者を挟まずに,消費者へ直接デリバリーできる技術が整ってきました。また,Webメディアでの露出があれば,我々がターゲットとする硬派なストラテジーゲームファンのほとんどに,ゲームの存在を知ってもらえるようになったのです。
Distant Gunsのファイルサイズは,わずか200MB以下。これをトライアルデモとしてダウンロードするのに,ためらう人はほとんどいないだろうと確信しています。
本作の場合,とくに何も購入しなくとも,ダウンロードしてから30日間,もしくは30回分のプレイが可能です。そのため,一つのキャンペーンを,一度なら十分に通して楽しむことができるんですよ。その後,もっと遊んでみたいと思ったら,シリアル番号を購入するというシステムです。
ちなみに,本作のプログラムはCDにコピーすることもできますが,シリアル登録をしたPC以外では,トライアルデモバージョンとしてインストールされる仕組みになっています。
実をいうと,一つ一つの質問に対してかなり詳しく説明してもらったのだが,高度に技術的な話が多かったので,割愛させていただく。
日露戦争がテーマという,歴史やミリタリーが好きな人にはたまらない存在の本格的ウォーゲーム,Distant Guns: The Russian-Japanese War at Seaは,近日中にリリースされる予定。今のところ,日本語版を開発する計画こそないらしいが,インターネットを使った自社流通や,太っ腹なトライアルデモによって,日本人でも手軽にプレイできるタイトルとなりそうだ。
もはや,パッケージ販売につきものの制約はおろか,“国境”という概念さえもなくなろうとしているのである。

次回もまた,とある開発者について紹介します。

