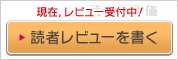インタビュー
謎多きベテラン作曲家“与猶啓至”氏。魅惑の80年代風シンセサウンド全開の「星霜鋼機ストラニア」でBGMを担当した氏に音楽の魅力と背景を聞く
 |
本作の作曲を担当した与猶啓至氏は,MSXやX68000といった国産PCの全盛期からゲーム音楽を手がけてきた大ベテランだが,その遍歴はこれまで意外なほど語られてこなかった。今回,「ストラニア」のBGMの魅力とともに,氏の素顔に迫ってみる。
MSXでデビューしX68000でFM音源を極める
筋金入りの研究者肌
 |
よろしくお願いします。ストラニアのプレイヤーの中には,この作品で初めて“与猶啓至”という作曲家を知った人も含まれると思います。与猶さんは,MSX2用ソフトとして発売された「ハイデフォス」(1989年)の作曲に始まり,かなりの数のゲーム音楽を手がけてきましたが,もしご自身の代表作を挙げるとすれば,どの作品になりますか?
 |
やはり「あすか120%」シリーズでしょうね。当時プレイしてくれた,多くの方に覚えていただけているのもそうですし,わりとポップでありながら,自分の研究者肌なところが,ちょうどいいバランスで入っています。
また,私ができる限りのことをやった作品なら,ゲーム音楽ではないのですが「サイバーフォニック」シリーズ,ある程度安定した,自分らしいサウンドを作ることができたゲームというと,「マッドストーカー」(1994年,X68000)になりますね。
4Gamer:
研究者肌というのは,どういったところがでしょうか。
与猶氏:
そうですね,僕は世の中に求められたり,好まれたりするような音を積極的に作っていくよりも,むしろ何かを探したり発見したりしながら作った音を,みなさんに届けていくのが好きなタイプなんですよ。
4Gamer:
なるほど。研究者肌というのは,そういった音の探索を指しているわけですね。
与猶氏:
ええ。でも,そのせいもあってコンポーザー仲間からはよく「新しいサウンドのヒントになる人」と言われたりします(笑)。僕が発見したサウンドデザインの手法を,ほかの人が上手に使ってくれるんですよ。
4Gamer:
与猶さんの新しい音作りが,ほかのコンポーザーにも影響を与えているんですね。
与猶氏:
ですので,僕が直接的にリスナーに与えている影響よりも,ほかのコンポーザーを通して,間接的に与えていることが大きいと思っています。以前はとくに,そんな感じでしたからね。
4Gamer:
ということは,現在は変わりつつあるわけですか。
与猶氏:
最近はわりと肩の力が抜けてきて,研究しながらの作曲は,意識しないとできなくなってきました。
もちろん「こんな曲で」というオファーがあれば,その方向性を意識しますが,何も要求がなければその場のノリというか,感覚的に作ることが多くなりました。
4Gamer:
その変化には,どういった理由があるのでしょうか。
与猶氏:
僕は音楽のことを,数学的,図形的というか,パズルのように捉えていました。そして,そんな風に解釈できる音楽こそが面白いという感覚を持っていたんです。でもその裏にあったのは,ある種のコンプレックスみたいなもので,感覚的にやっていたのでは,ほかの音楽家には太刀打ちできる気がしなかったんですよ。
知的な要素とか,何かしら新しいものを提案していかなければ,独自性は出せないと信じていたので,トリッキーなことやイレギュラーなことを,ギリギリまで入れてきました。
4Gamer:
そうして生まれたのが“与猶サウンド”だったというわけですね。
 あすか120% BURNING Fest. |
 マッドストーカー |
美少女ゲームからアーケードゲームへ
インターネットがもたらした化学反応
4Gamer:
与猶さんは,90年代にPCエンジン作品である「あすか120% BURNING Fest.」といったコンシューマ機を中心に活躍していましたが,その後の活動の場を,PC美少女ゲームに移されましたね。10年以上が経って,今回アーケードゲームのストラニアでBGMを担当したわけですが,そのきっかけはどのようなものだったのでしょうか?
 |
最初は「KORG DS-10」(NDS)でアマチュア活動をしていて,イベントをやったり,YouTubeやニコニコ動画に動画をアップロードしていたんです。そうしたら,グレフの丸山博幸社長がそれを観てくれていたらしくて。
丸山さんはもともと,僕の昔のゲーム音楽をご存知だったそうで,「ニューラルギア」(1990年,X68000)や「マッドストーカー」あたりのサウンドのビジョンが,ちょうどストラニアに合っていたんだそうです。
そこで,僕にコンタクトを取ってくれて,では一度お会いしましょうというお話になったんです。
4Gamer:
ということは,丸山さんは昔からの与猶ファンではあったものの,とくに繋がりがあったわけではないんですね。アマチュア活動によって初めて繋がりができたというのは面白いです。
与猶氏:
そこは動画配信サイトというツールに助けられたと思います。そのことがあってから,ストラニアの仕事を受けるまで時間はかからなくて,まだリリースまで期間もあったので,しっかりとサウンドをやっていきましょうということになりました。
4Gamer:
ストラニアのサウンドのビジョンが,「ニューラルギア」などと合っていたということですが,ストラニアでの作曲を受けた時点で,サウンドのコンセプトはもう「80年代風」と決まっていたんですか?
与猶氏:
ええ。昔のサウンドを再現しつつ,これまでの経験や現在の視点から,新しいアイデアを入れてもらいたいという話でした。
サントラCDは「ストラニアサイド」(通常BGM)と「バウアーサイド」(追加コンテンツ用BGM)で内容が分かれていますが,「ストラニアサイド」は昔ながらの雰囲気というオーダーだったので,作り方や音色が昔風になっています。その一方で「バウアーサイド」は,「今ならこういう風にしたい!」という思いでやってみた音になっています。
4Gamer:
与猶さんの過去と今をそれぞれの作品に込めているわけですか。ちなみに昔風ということですが,意識したタイトルはありますか。
 |
ストラニアのサウンドコンセプトを話し合う中で,自然に出てくる作品名が「ニューラルギア」だったので,これでしょうね。発注されたときも,やはりシューティング繋がりということもあって,「ニューラルギアみたいな感じで」と,何度も言われていました。
4Gamer:
それにしても,「ニューラルギア」を知っていたということは,丸山さんは本当に古くからのファンで,しかもかなりディープなゲーム音楽リスナーだったようですね。
与猶氏:
年齢は僕とそんなに変わらないので,社会人になったころに聴いてくれていたんでしょう。その後,僕は美少女PCゲームに行ったので,どこでどんな音楽をやっているのか,追いかけにくくなっていたと思うのですが,当時の音楽をしっかり覚えてくれていました。
4Gamer:
ところで,ストラニアの与猶さんだけではなく,「トリガーハート エグゼリカ」の音楽を手がけた梶原正裕さん,残念なことに先日亡くなられた「赤い刀」の梅本 竜さんなど,かつてPC-9801やX68000で活躍しておられたPCゲーム系の作曲家が,最近アーケードシューティングを舞台に活躍することが増えています。
PCゲームの開発とアーケードゲームの開発は,ほとんど接点がない分野ですが,なぜ最近になってこのような変化が起きていると思いますか。
与猶氏:
それは僕らが何かをしたと言うよりも,おそらく古い作品……僕で言えば「ニューラルギア」,梶原さんで言えば「プリンセスメーカー」,梅本さんで言えば「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」を,プレイヤーの立場で聴いていた人達がゲーム業界に入り,いまゲームを作る側の中心になっているからではないですか。音楽家に誰を起用するかについても選択権を持つようになったので,昔からファンだった音楽家を使い始めているんだと思います。
4Gamer:
80年代〜90年代のコアなゲームプレイヤーは,PCだけとか,アーケードだけとか,コンシューマだけとかじゃなくて,特定のプラットフォームにあまり偏らずにゲームなら何でも一通りやってみるという人が多かったように思います。そういう世代の人達だからこそ,PCゲーム出身の作曲家でも抵抗なく起用できたというところなんでしょうね。
与猶氏:
ファンだからこそ,ほかの分野でも羽ばたいてもらいたい。そんな気持ちもあるんじゃないでしょうか。
グレフさんは音楽に大きなこだわりを持っていて,Yack.(渡部恭久)さん(※1)がほぼ専属で,今でも現役バリバリで凄い曲を書いています。また最近ではスーパースィープの安井洋介さん(※2)というスキルの高い作曲家さんも起用しています。そんな中での採用ですので,非常にプレッシャーがありました。
仕事が終わるまでは,あまり意識してもいけないので,お二人の作品は聴かないようにしていたくらいです(笑)。でも,そうしてできあがった音に対してリスナーさんから,「Yack.さんみたいな音だね」と言われたりして,驚きました。
4Gamer:
そんな反応があったんですか。どちらもFM音源世代ということで,どこかに通じるところがあったのかもしれませんね。
世の中に存在しない音楽を生み出してきた
“与猶流作曲哲学”
4Gamer:
少し与猶さんの“作曲”についての考え方を聞かせてください。デジタルシンセらしい音を積極的に使っているのに,いわゆる「テクノサウンド」にはなっていなくて,コードやメロディの表現がきわめて多彩であるというのが,与猶さん特有のスタイルではないかと思います。これはどうやって確立されたものでしょうか?
 |
もともとシンセサイザー好きで,テクノも好きだったんですけど,ほかにも好きな音楽はいっぱいあるんですよ。だから自分の好きなものを全部詰め込んでいって,矛盾なく融合させたらどうなるのかをやってみたんです。
しかし,発想自体は非常に単純なんですが,実現のプロセスではいろいろな困難がありました。バッハを研究したり,フュージョンを紐解いたり,ハウスやテクノをいじくり倒したりしてましたね。
4Gamer:
バッハとフュージョンとクラブミュージック,すごい組み合わせですね。
与猶氏:
そう見えるんですけど,“その三つはそれほど違う分野ではないはずだ”“一緒の場所に置けるはずだ”という,根拠のない思い込みがありました。でも一緒にした楽曲が世の中にないから,これはやってみる価値があるだろうと思ったんですよ。
そうやって,あれこれ詰め込んで行くうちに,親和性の高い要素と,あまり馴染まない要素が見えてきて。
あと,作りやすさを追求したところもありますね。「自分はこんな楽曲を作りたい」という構想が最初にあるわけですが,それに合わせやすいようにしておく。あまりスタイルにがんじ搦めにされると,今度は表現のほうが窮屈になってしまうので,そういったところをどんどんシンプルにしていくうちに,現在の形になっていきました。
4Gamer:
現在の形はあくまで結果であって,「シンセサイザーをこう使ってやろう」と意図していたわけではないんですね。
与猶氏:
そうですね。最初は音色じゃなくて,むしろ音符のほうに意識がすごく向いていました。でも最近は,音色を作り込むほうが楽しくなってきたというか,音色にこだわって作っているほうがモチベーションが上がります。逆に音符のことはもうやり尽くした感があります。あまり意識しなくても,昔どおりの構成力で,無意識に曲を書けるようになってきたというか。
4Gamer:
ちょっと意外ですね。与猶さんの曲はFM音源やPSG音源のころから,かなり音色にこだわっていたという印象があるので。
与猶氏:
限られた環境だったので,音色を改良するしかなかったんです。音符の上では「こう聴こえるはず」と思って設計したものが,実際に鳴らしてみるとそのとおりに聴こえないということが,当時はよくありましたから。僕の気持ちでは,あくまで音符優先だったんですよ。
4Gamer:
音符を補うものとして音色があったわけですね。音符の話でいえば,与猶さんの曲はベースラインがきわめて特徴的ですが,どうしてあれほどまでベースを強調するように?
与猶氏:
ベースが「歌っている」(※単にコードの一要素としてではなく,独立したメロディアスな楽器として機能している)ことの気持ちよさを意識するようになったのは,アース・ウインド・アンド・ファイアー(※3)を聴いてからですね。すべてに無駄がなく,そこが僕の好きなバッハと共通していると思いました。チョッパーベース中心の音づくりは,もろにゲーム音楽の影響です。当時X68000版「ボスコニアン」(作曲・古代裕三氏)とか,セガの「ギャラクシーフォース」を聴いていたんですが,FM音源という限られた環境のなかでは,ベースのウエイトが非常に高いというか,リズムとベースだけでもかなりの表現力があると感じていたんです。
極端な話,仮にほかの部分がいい加減だったとしても,そこだけしっかりしていれば大丈夫というくらいに思っていました。
4Gamer:
なるほど,クラブ(ディスコ)ミュージックが始まりだったんですか。与猶さんは1990年代,ゲーム音楽のなかにハウスやテクノといったクラブミュージックの要素をいち早く採り入れていったわけですが,なぜそこにアプローチしようと考えたのでしょうか?
与猶氏:
流行っていたからというのももちろんあるんですが,クラブミュージックには,なんといってもスピード感とかノリといった部分が大きいです。それを生かしてリフレイン(印象的なワンフレーズを何度も繰り返すこと)を強化するテクニックが,ハウスやテクノの中には非常に多くあります。自分の「細かく入り組んだ音」の底辺を支えるものとして,それが欲しかったんです。
4Gamer:
当時のテクノやハウスはまだ異端の音楽と言うか,一般の音楽シーンでは受け容れられていない,生まれたばかりの荒削りなジャンルでしたよね。バッハやフュージョンなどの完成された音楽とは,反対の位置にあったと思うのですが,それを採り入れることに抵抗はなかった?
与猶氏:
なかったです。むしろ「普通にやるべきものだ」「音楽はいずれこうなっていくんだ」という気持ちがありました。また根拠のない確信ですけど(笑)。
4Gamer:
そうした直感が,与猶さんの音楽を生み出しているんですね(笑)。そうして自身の作風を確立されたあと,与猶さんはコンシューマ機の舞台から離れ,PCの美少女ゲームに活動の中心を移していきました。あえて美少女ゲームに向かわれたのはなぜですか?
与猶氏:
コンシューマゲームと,接点がなくなってしまったことが一つですね。オファーがあれば,もちろんやりたかったんですが。ただPCゲームで使われるような音楽は,それまでやってきた自分の音楽とまったく違っていて,当時の自分にはまるでできない分野でした。でも「いや,自分にもできるはず。できるようになろう」と,そちらに強く意識が向いていました。
4Gamer:
できないからこそ逆に「自分にできる何か新しいこと」を探ってみたわけですね。そうした変化を求めた与猶さんですが,それでも変わらなかったことはありますか?
与猶氏:
ハーモニーの面白さを追求するところですね。今の時代にその面白さが求められている気はあまりしませんが,自分が面白いと思わないところには,なかなか手が出ませんから(笑)。
キーワード
- Xbox360:星霜鋼機ストラニア
- Xbox360
- シューティング
- Xbox LIVE アーケード
- グレフ
- ロボット
- 協力プレイ
- ARCADE:星霜鋼機ストラニア
- ARCADE
- インタビュー
- ライター:hally
(C)2009,2011 G.rev Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2009,2011 G.rev Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.