連載
メガテンの生みの親,岡田耕始氏が自身を捧げたRPGという祭(後編)アトラスの栄華と迷走,そして新たな挑戦 ビデオゲームの語り部たち:第32部
 |
今回の「ビデオゲームの語り部たち」では,前回に引き続き,岡田耕始氏の歩みを紹介する。
「女神転生」シリーズを発展させた「真・女神転生」シリーズや,その派生作品の開発,アトラスの絶頂期とその後の経営悪化,そして自身のアトラス退職と会社立ち上げなど,激動の時代を語っていただいた。
筆者は今回岡田氏の話をうかがって,氏やアトラスが,人の行かない“裏道”を見つけ,そこを進んだからこそ,大きな成功を手にできたのだと感じた。もちろん,裏道には危険も潜んでいるのだが,そこに敢えて踏み出す勇気がなければ,多くの人と同じようなものしか得られないのだろう。そんな道を歩んできた岡田氏の言葉には,人を惹きつける何かがある。読者の方にそれを感じてもらえれば嬉しい。
 |
メガテンの生みの親,岡田耕始氏が自身を捧げたRPGという祭(前編)アトラス立ち上げと初代「女神転生」 ビデオゲームの語り部たち:第31部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」。今回は,「女神転生」シリーズの生みの親である岡田耕始氏に,自身の学生時代やアトラス設立,そして初代「女神転生」の開発エピソードなどを語っていただきました。
結果的に「東京」「宗教」「悪魔」がテーマになった女神転生
それまでにないシステムやサウンド,独特の世界観などが評価され,ヒットした「デジタル・デビル物語 女神転生」。しかし岡田氏は続編の「女神転生II」で,原作小説とはかけ離れた世界設定のゲームを作り上げ,スーパーファミコン向けとなるにあたって再び設定を見直し,タイトル名も「真・女神転生」と改めた。これには,岡田氏の性格が大きく影響しているようだ。
「私も『Wizardry』や『Ultima』などの影響を受けたとはいえ,それをそのままメガテンに持ち込んだわけじゃない。バンドにしろプラモデルにしろ,スコアとか設計図通りにやるのは好きじゃないんです。プラモデルならジオラマを作ったり,表面をちょっと溶かしてみたり。
遊びなら『こうやったら面白いんじゃないか』と,今で言うローカルルールを作ったり。『UNO』に麻雀の役みたいな要素を入れて,手札がたくさんあっても一気に上がれるルールを作ったこともあります。とにかく人と同じなのが嫌だった」
前回紹介したように,「女神転生」は西谷 史氏の小説「デジタル・デビル・ストーリー」から生まれたタイトルだが,西谷氏からはゲームについて注文のようなものはなかった。「真・女神転生」となるにあたっても,それは同じだったようだ。
アトラスの社長だった原野直也氏と西谷氏が古い知り合いだったことを差し引いても,“寛大な処置”だったと言っていいだろう。
ファミコン向けの「女神転生」シリーズ2作がナムコからリリースされていたにも関わらず,「真・女神転生」がアトラスの自社パブリッシングとなったことについても,似たようなエピソードがある。
「原野さんと一緒に,ナムコの中村会長(中村雅哉氏)のところへうかがって,『アトラスから出させてください』とお願いしたら,快諾していただいたいて。なぜ許してくれたのか,確かな理由は分からないけど,言えるのは,『女神転生』の商標をアトラスが持ってたことと, 原野さんと中村会長の信頼関係があったからじゃないかな」
こういった人の縁に恵まれたこともあって,岡田氏は自由に開発を進めることができたのだろう。
「女神転生」シリーズでは,「ヤクザ」や「ボディコニアン」など,そのときどきの東京の世情を反映しているキャラクターが登場するのも印象的だが,これは岡田氏自身と,デザイナーの金子一馬氏※のセンスによるところが大きいようだ。
※多くのアトラス作品でキャラクターデザインを手がけた“悪魔絵師”として知られる
「世界観のベースには宗教的なところがあるんだけど,2人とも東京で生まれ育ったこともあって,まさにその当時の東京をゲームに反映させていたんです。
世界を見ても,これだけ変化に富んだ都市はないんですよ。100年の間に明治維新があって,関東大震災があって,東京大空襲があって……。ゼロに近い状態から再生して,これだけの大都市になった。私も仕事で海外には何度も行きましたけど,東京のような規模で政治やエンターテイメントが集約されているところはない。文化もそうですよね。浅草寺の五重塔を見ても,子どもの頃は何とも思わなかったけど,今はすごいと感じています」
 |
 |
前編では,岡田氏が生まれて以来,東京の元浅草に住み続けていることや,祭り好きであることを紹介したが,やはりこのあたりは女神転生に少なからず影響を与えているようだ。
悪魔(女神転生シリーズでは,さまざまな宗教上の神もこう呼称する)をゲームの題材として扱うことになったのも,自身の“生まれ”が関係していると考えているという。
「東京もそうだし,もともと日本自体が,ある意味何でも受け入れちゃうところがある。例えば宗教は,鎖国していた時代もあるけど,結果的には仏教,神道,キリスト教,そのほかの宗教が混在している。昔はお寺と神社が一緒だったし。そもそも神道は宗教じゃないという考え方もあって,調べていくと『日本人の根源とは?」みたいな話になっていく。
女神転生では,そういうところを見せたいと思ったんです。悪魔を出すことによって,インドから入ってきた宗教が,変化して日本に根付いた……といったことを示す。当初はそこまで考えてなかったけど,結果的にそうなったし,一生かけても語り尽くせないテーマになった」
「当初はそこまで考えてなかったけど」と話したように,岡田氏はシリーズ作品を重ねていく中で,さまざまな宗教について調べながら女神転生の世界を深めていった。
「悪魔合体は,悪魔の数が多くないと面白くないと思ったんですが,ファミコン用のROMでは容量が足りなくて。スーパーファミコン用の『真・女神転生』でようやく200種類以上の悪魔を入れられるようになったので,いろいろな宗教を調べました。
それまで聖書なんて手に取ってこなかったから,旧約聖書を読んで『え,何でキリスト出てこないの?』とか(笑)。新約聖書でも『福音書って,キリストが書いたわけじゃねえんだ』『字が読めない人もいるのに,何でこんなに普及したんだろう』とかね」
そうやって開発されたシリーズ作品がヒットを重ねていったことはご存じの通りだが,岡田氏の予想もしなかったところにも影響を与えていた。
とくに印象に残っているのは,2008年5月24日と25日の両日,東京大学五月祭での講演を依頼されたときだという。
「『何で東大に?』と思って主催者の学生に話を聞いてみたら,メガテンで興味を持ってインド哲学を専攻したって。『え,あなたの人生変えちゃったの!?』とビックリしましたね」
派生タイトルの開発とともに世代交代を進める
「女神転生」シリーズは,「ペルソナ」「デビルサマナー」「アバタール・チューナー」といった,多彩な派生シリーズでも知られている。そのきっかけが生まれたのは,岡田氏が「真・女神転生II」を作り終えた後,次作への意欲が湧かず,燃え尽き症候群のようになっていた時期だったという。普通に考えれば「III」となるのだろうが,岡田氏が“既定路線”に乗らないことは,ここまで読んでいただいた方にはお分かりだろう。
「そこで金子と話して,今までマクロ的な視点のものを作ってきたから,テーマ的にミクロな学園ものをやってみよう,と『真・女神転生if...』の企画を立ち上げたんです。あれは半年で作ったんですよ。システム的には『真・女神転生II』と一緒だという指摘もありましたが,結構面白いと評価してもらえました」
 |
 |
岡田氏が「真・女神転生if...」を開発していたのは,発売を控えた初代PlayStationとセガサターンが準備を進めていた時期に当たる。当然ながら人気シリーズを抱える岡田氏には,両陣営からのオファーがあった。
「ソニー(当時)の吉田さん(現SIE ワールドワイド・スタジオ プレジデントの吉田修平氏)がわざわざ来てくれて,『メガテンが大好きだから,ぜひPlayStationに出してほしい』と言ってくれたんです。それで『if...』の流れで,同じ学園ものの『女神異聞録ペルソナ』を企画しました。
セガからも営業取締役の毛塚さん(毛塚敏郎氏)が来て,『ぜひセガサターンで』と。こちらには刑事ドラマや探偵ものの要素を入れた『真・女神転生デビルサマナー』を開発しました。もともとは刑事を主人公にしたかったんですけど,それだと制約が多くてストーリー展開が難しいんですよね。それで探偵にして,そこに陰陽師の要素を入れて。
この2作はほぼ同時期に,少ないスタッフを2チームに分けて作ってたんです」
なお「女神異聞録ペルソナ」は,もともとシンプルな「ペルソナ」という名称だったが,当時のアトラスの営業部長の意見により変更されたとのこと。
「『え,メガテンじゃねえの? ペルソナって何?』って。『“仮面”って意味です』って答えたら,『そんなの誰も知らない。売れないからメガテンって付けてよ』って言われちゃって。こっちとしては『知らないのを知らしめるのが営業だろ』と思ったけど,営業部長に売れないと言われたら仕方ないから,金子とふたりで徹夜で考えて,翌日『“女神異聞録”って付けて』って提案したんです。おかげさまで売れたんだけど,それを見て営業部長は『“女神異聞録”って要らなかったな』って。もう,ふざけんなと(笑)」
 |
 |
「真・女神転生デビルサマナー」も,当初はシンプルに「デビルサマナー」というタイトル名だったという。当時は“サマナー”(召喚者)という言葉があまり浸透していなかったため,やはり売れないと判断されたそうだ。新規IPの立ち上げには,こういった面でも難しさがつきまとうのだろう。
岡田氏はこの頃から,ディレクターやプロデューサーとして「女神転生」シリーズに取り組んでいくこととなった。
「それまでは自分で企画してプログラムを組んでいたけど,30歳になったときに,もうプログラマーとしては無理だと思ったんです。ゲーム開発でも,ようやくディレクターという肩書きが浸透し始めた頃だったので,じゃあそれでいいかと。
会社としても,次の世代に継承していかなきゃってことで,キャラクターデザインも金子の一番弟子だった副島(副島成記氏)に任せればいいんじゃないかと,世代交代を進めていきました。
おかげさまで『ペルソナ』はそのままシリーズとして残ってるし,『デビルサマナー』も『ソウルハッカーズ』シリーズに発展しています」
プリクラの成功で迎えたアトラス絶頂期
4Gamer読者のようなゲーマーにとってのアトラスは,当然ながらゲーム会社だと思うが,世間的には「プリント倶楽部」,通称プリクラの会社としてもよく知られている。岡田氏は,プリクラの開発にも関わっている。
 |
「プリクラは,もともと原野さんのところに外部から持ち込まれた企画で,『自分の写真をシールにできる』というだけの内容だったんです。売れるかどうか分からないけど,作ってみるかという話になって。
でもアトラスはハードウェアを作っていなかったから,いくつかパブリッシャを当たって,セガへ持っていったら,当時の社長の中山さん(中山隼雄氏)が『やろう』と」
だがこの時点では,アトラスもセガも,プリクラの魅力がどこにあり,どんな人に響くものなのか分かっていなかったようだ。
「アーケードゲームと同じようにゲームセンターでロケテストをしたら,全然反応がない。今思えば1990年代半ばの格闘ゲーム全盛期で,ゲームセンターには“格ゲー男子”しかいませんでしたから,いきなりそんなものを置いても使わないですよね。それで,『これは難しい』って話になったんです」
それほど期待されていなかったプリクラの転機となったのは,1995年2月に開催されたAOUアミューズメントエキスポだった。
「出展したら,会場のブースにいるコンパニオンたちが空き時間にやってきて,長蛇の列ができたんです。
そこで思い当たったんですが,プリクラ以前にも,カップルや女の子同士が証明写真機に入って,同じような遊びをやっていたんです。でも証明写真だと4枚くらいだし,シールにもならない」
写真がシールになっていれば,好きなところへすぐに貼れる。数が多ければ,友人に配ることもできる。プリクラは,新しいものに敏感な女性たちの表現手段やコミュニケーションツールとしてぴったりだった。妙な例えになるが,アナログ版Instagramといえば分かりやすいだろうか。
「おそらくですが,持ち込まれた企画も,もともとはカップルや女の子をターゲットにしてたんでしょうね」
会社の上層部から現場に降りてくるまでの間に,企画のコンセプトやターゲットが見えづらくなってしまっていたということだろう。プリクラの開発チームは,幸運にもそれに気づくことができた。1995年7月のプリクラ本稼働にあたって,アトラスはさまざまな施策を展開していく。
「当時のプリント技術を踏まえると原価が200円くらいになるから,当初は1回500円くらいを考えていたんです。でも,女性の意見を聞いてみると『高い』と。300円ならやるという声が多かったので,利益が少なくなるけど1回300円にしました」
女神転生のキャラクターにもお呼びがかかった。
「女の子向けに可愛らしい案内役が必要だということで,ジャックフロストに操作を説明させる仕様にしていたんです。
でも,ゲームマニア以外の一般の方は女神転生を知らないから,いつの間にか“プリクラ太郎”と呼ばれるようになりましたけど(笑)」
 |
プリクラの認知度を一気に高めたのは,あるアイドルグループだった。
「アトラス入社前にシンコーミュージックに務めていて,音楽業界とつながりのあった峰岸さん(峰岸不二男氏)のツテを使って,当時人気だったテレビ番組の『愛ラブSMAP!』で,SMAPのメンバーが撮ったプリクラをプレゼントする企画をやったんです。それを見た子たちが『何あれ?』ってゲーセンに来るようになって」
こういった苦労や努力の甲斐あって,プリクラは爆発的なブームを巻き起こした。
「もうドーン! とヒットした。シールがお札に見えるくらい(笑)。あの時期は『ペルソナ』や『デビルサマナー』が出て,プリクラも大ヒットして,アトラスは絶好調でした。そして1997年に株式の店頭公開をしました。そこからもドーン! ドーン! と株価が上がっていって……」
 |
ある意味で自然な成り行きではあるのだが,この時に株を売った創業時のメンバーもいた。その中には,都内の一等地に豪邸を建てたり,高級車を4,5台購入したりといった人もいたという。
岡田氏もこのとき,持っていた株の一部を売ったが,こういった人たちに比べれば“可愛いもの”だったそうだ。
「海賊」と呼ばれた原野氏率いるアトラスが,危険な航海の末,ついに“お宝”を見つけた……そう表現したくなるような,夢のあるサクセスストーリーだ。
ところで,ゲーム会社のアトラスが,なぜ畑違いとも思えるプリクラの企画にGOサインを出したのか,不思議に思う人もいるかもしれない。
だが当時のアトラスはゲーム会社というわけでなく,実際のところ“多角経営”の会社だったようだ。岡田氏の話によると,アトラスは日本で最初にカラオケボックスを製品化した会社でもあるという。
「アトラスがメガテンとプリクラだけの会社じゃないってことを,もっと世間に知ってほしいんですけどね。
1980年代の半ばごろ,『広島では国鉄が払い下げたコンテナの中で主婦がカラオケをやっている』って話が原野さんのところに持ち込まれたんですよ。『何だ,そりゃ?』って現地に見に行ったら,噂通り,コンテナに8トラックのカラオケマシンを持ち込んで,主に女性が昼間から歌い上げていたんです。
それで原野さんが『アトラスでやろう。岡田,お前設計やってたよな』って言うんですけど,私は私でメガテン作ってるから『できません』と。それでエアコン完備のボックスを作って,レーザーディスクのカラオケ機材を入れて……という工程のチェックだけ,私がやることになりました。
だからカラオケ事業を始めた1989年頃のアトラスは,第一興商の一番の得意先だったんです」
それと同じ頃に起こっていたプールバー(ビリヤード台を置いたバー)のブームにも,アトラスが一枚かんでいるという。
「私は個人的にビリヤードにハマっていたんですが,その頃のビリヤード場は廃れてきていて,都内にも数えるほどしかなかったんですよ。でも原野さんが台湾で安くビリヤード台を作れるという話を聞きつけてきて,『昔は飲み屋でビリヤードができたんだ』と,杉並の浜田山にプールバーの1号店を作ったんです。そのときアトラスは,経営じゃなくて施工だけを担当していたと思います。
原野さんは,そうやってどこかから持ち込まれた話を形にしてビジネスにつなげる人でした」
世間的に,プールバーブームの発端は,1986年に公開されたポール・ニューマンとトム・クルーズ主演の映画「ハスラー2」とされることが多いが,アトラスはその流れに乗ったわけではなかったという。原野氏にはやはり商機を見る目があったのかと思うが,岡田氏は……。
「失敗もたくさんあるんですよ。例えばスロットレーシングを設置したショップを作ったり,ビリヤードの“簡易版”として,テーブルの上でカーリングみたいなことをやる遊びのビジネスを鳴り物入りで始めたりしたけど,うまくいかなかった。プリクラのロケテストも,いきなりゲーマーしかいないゲーセンに置いて失敗したり(笑)」
アトラス退職とガイア設立
株式公開によってアトラスは多額の資金を調達したが,それを新たな展開の成功につなげることはできなかった。岡田氏は,結局のところゲームの延長線上でしか考えられなかったと語る。
「ゲームセンターをいっぱい作るとか,タイトルを増やすとか……。でもゲーム開発を岡田・金子体制でやってたら,メガテンは2年に1本しか出せない。
株式公開に伴って銀行から来た役員の提案に沿って,第2,第3と開発ラインを増やしてみても,なかなかうまくいかない。結局,メガテンしか残らなくて……という結末になったんです」
そして岡田氏は,2003年にアトラスを退社する。
「アトラスを辞めた一番の理由は,ほかの会社から資本が入ってきたからです。プリクラがバカ当りして株式を店頭公開したけど,1999年度から売上が落ちていって,会社が外部からの資本提供を受け入れる判断をした。
最初は角川書店だったんだけど,そのうちタカラの連結子会社になって。それでタカラがトミーと合併してタカラトミーになって,ついにはゲームと無縁のインデックスみたいなところが資本に入ってきて……その頃はもうアトラスから離れてましたけど,これは違うなと思いましたね」
アトラスが角川書店と資本業務提携を結んだのは2000年,それを解消してタカラの連結子会社となったのは2003年のことだ。このときタカラはコナミのグループ会社だったが,コナミが2005年にタカラ株をインデックスに売却したことで,タカラはインデックス傘下に入った。
そしてタカラは2006年にトミーと合併してタカラトミーとなり,同年インデックスはアトラスの株をタカラトミーより取得して,アトラスはインデックスの連結子会社となった。
経緯を書き出すだけでも,アトラスが“迷走状態”にあったことは分かるだろう。当初は“相手を選ぶ”こともできていただろうが,やがて“自分の知らないところで親が変わる”といった状況になっていったと思われる。
まさしく絶頂にあった1997年の株式店頭公開から10年も経たないうちに,アトラスを取り巻く状況は一変してしまった。まさに一寸先は闇,企業経営というものの難しさ,得体の知れなさを感じる。
なお,その後インデックスの民事再生手続きを経て,アトラスが現在セガサミーホールディングスの傘下にあることは,多くの方がご存じの通りだ。
話を岡田氏に戻そう。アトラスを辞めた岡田氏は,自身の会社であるガイアを設立した。
「周囲には『岡田と言えばメガテン』みたいなイメージがあったんでしょうけど,私自身には,アトラス時代と同じようなもの作るという発想はなかったですね。アトラスを辞めるときには,もう世代交代もほぼ終わっていたし,やりきった感があったんです」
ガイアは,まずPlayStation 2用タイトルの大型プロジェクトに着手したが,うまくいかなかったという。
「当時はネットワークが流行り始めていたので,全世界をつないだ仮想空間を作ろうとしていました。ネット上でなんでもできるようなバーチャル空間,今で言うところのメタバースのようなものです。まさにニューヨークや上海をバーチャルシティとして再現しようとしたんだけど,やりたいことに当時のネットワーク技術が伴わなくて,プレイヤー同士がつながるところまでしか行けなかった。確か発表もしたんだけど,手を広げ過ぎて,収拾が付かなくなったんです」
岡田氏がプロデューサー的な役割を担わざるを得なかったことも,開発が難航した要因だと考えているとのこと。
「もっとディレクターに徹することができればよかったんだろうけど。それで原点回帰というか,次はいい意味で少し小さいタイトルをやろうと。PSPでカプコンさんの『モンスターハンター』シリーズがドーンと売れていたんで,携帯機で何かできたらいいなと考えました」
そうして,PSPやニンテンドーDS向けタイトルを開発するようになったガイアだったが,成功は違うところから生まれた。2010年にリリースしたスマートフォンゲームの「Sword & Poker」だ。ガイアが企画開発した同作は,世界中でヒットした。
 |
 |
 |
「ファミコンやPlayStation,セガサターンが出てきたとき,いつもそれに乗っかってゲームを作ってきたんですよね。実はガラケーが出てきたときも,同じようにゲームを作りたかったんですよ。でも『ペルソナ』などもあったので,そこまで手が回らなかった。
それでiPhoneが出てきたときに,『画面に触れるゲームは面白い』『これ用のゲームを絶対作ろう』と思ったんです。
ちょうど,従来のコンシューマゲーム機向けでは思ってるものが作れないと考えてたところだったので,スマホゲームに舵を切ろうとAppleと契約して。まあ,売上の30%をAppleに持ってかれちゃうんだけどね(笑)」
「Sword & Poker」は,ポーカーをモチーフにしたカードバトルを特徴とするステージクリア型のRPGである。
「最初に,全世界の誰もが知ってるルールのバトルで,RPGを作れないかと考えました。メガテンでは,カジノ系のミニゲームが結構好評だったし,私自身もそういうのを企画するのが好きだったんで,その延長線上でポーカーにしようと。
でも,それだけでは面白くないんで,5×5マスの盤面上にビンゴのようにカードを組み合わせて役を作っていくバトルにして。そのバトルを繰り返しながら,ダンジョンを進んでいくRPGにしようと考えたんです」
「Sword & Poker」のヒットは注目を集め,2013年にはKONAMIから「ドラコレ&ポーカー」が配信された。このタイトルは,「Sword & Poker」と,当時大ヒットしていたKONAMIのソーシャルゲーム「ドラゴンコレクション」(以下,ドラコレ)のコラボにより実現したものだ。
「KONAMIさんのどなたかが『Sword & Poker』にドハマリしていたそうで,当時大人気だったドラコレとコラボしませんかと誘っていただきました。コラボと言っても全部先方にお預けしたんですけどね。ドラコレのような大ヒットタイトルのノウハウは,ガイアにはなかったし。
今思えば,課金面も含めてもうちょっと勉強して,本当の意味でのコラボができればよかったんですけど,ドラコレは『パズル&ドラゴンズ』が登場する前では最大規模のタイトルだったから,ついお預けしちゃった」
「Sword & Poker」は今でも世界中でプレイされている(日本国内向けの配信は行われていない)。
「不思議ですよね。もう12年前のタイトルなのに,そこそこ売上がある。誰が遊んでるんだろうと思っちゃう。それに,いつの間にか『Sword & Poker』がイギリスで賞を取ってるんですよ。私には知らされてないのに(笑)。
ほかにも,いきなりフランス語の招待状が来て,『何だこれ?』と思って問い合わせたら,『南フランスのモンペリエでゲームショーをやるんで,来ていただけませんかという招待です』と」
ファーストクラスのチケットをもらい,フランスへ飛んだ岡田氏を待っていたのは,「Sword & Poker」への賞賛だけではなかった。
「会場に行ったらスタンディングオベーションですよ。『何で?』って思ったら,フランスの皆さんは『Sword & Poker』だけでなく,メガテンも知っていると。日本に来たことのない女性が,『メガテンがやりたくて,日本語を勉強しました』と日本語で話してくれるんですよ。そんな機会が2回もあって。フランスはものを作る人に対するリスペクトが強いことを実感しました」
岡田氏は今もなお,国内外の人から「メガテンのようなゲームを作らないんですか?」と尋ねられるという。
「ガイアを立ち上げたときにも『作ればいいのに』とさんざん言われましたけど,さすがに作れねえだろうと」
もちろん「女神転生」への興味を失ったわけではなく,シリーズへの思いは今なお強い。
「『ペルソナ』は,私がやってたときも何回かアニメ化の話があったんです。ただ版権の問題で,ことごとく頓挫しちゃって。でも私が離れた後,アニプレックスがうまくやってくれた。金子路線から弟子の副島路線にうまく引き継げたとも感じているし,そういう種を蒔けたのはよかったなと。
『真・女神転生』シリーズについては,正直に言えば『ちょっと違うかな……』と思うところもありますが,それは自分の手を離れたものですからね」
岡田氏がこう話すわけには,「真・女神転生III」を展開させている途中でアトラスを離れたことがあるかもしれない。退職について「やりきった」と語った岡田氏だが,ここについては若干の心残りがあるようだ。
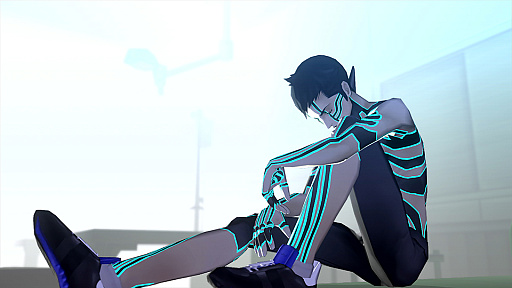 |
「『真・女神転生III』に,“序章”という意味の“NOCTURNE”と付けたのは,『IV』までに『III』をもっと展開しようと考えていたからです。さらにコアなファン向けに,『NOCTURNE マニアクス』を出して。そうやってナンバリングをいろんな形で展開したかったんだけど,結局私がアトラスを離れることになっちゃったから」
具体的な構想が頭の中に残っているからこそ,それとの違いが気になってしまうのだろう。子どもに任せようと思っても,つい口が出てしまう親のような愛情を感じる。
 |
人との出会いに恵まれた岡田氏が見据える将来
岡田氏は自身の半生について,「人との出会いに恵まれた」と語った。出会った人を“師”と仰ぎ,ここまで歩んできたという。
「原野さんは当時から人と人をつないだり,困っていると助けてくれたりしてくれて,今でのいうところのエンジェル投資家みたいな人でしたね。印象に残っているのは,プリクラがヒットした時のことです。他社のゲームを置かないプリクラ専用のアーケードを作ろうという話が役員会で出たんですが,原野さんは『自分たちだけが儲けるのはダメだ』と言って反対したんですよ。自己の利益だけでなく、他社との共存や利益を考えていたんではないでしょうか。自分にとって原野さんは『人生の師』で,『プログラムの師』は石塚さん,『企画の師』は上田(和敏)さんなんです。息子達にも『人とのつながりは大事だから』と,ずっと言い続けています」
ほかにも,デザインを手がけた金子氏の尽力,原作者である西谷氏やナムコの中村氏の厚意がなければ,女神転生の運命が変わっていたかもしれないことは,本稿ですでに紹介した通りだ。また,前編を読んでいただいた方ならご存じの通り,ユニバーサルで横山秀幸氏(現ガンホー・オンラインエンターテイメント執行役員)の隣の席になったことが,テーカンへの移籍,そしてアトラスにつながっていったのだから,岡田氏の言葉には現実味がある。
 |
そして岡田氏は,自身を支えてくれる家族にも恵まれた。
「こないだ,結婚32周年を迎えたんですが,今は32年分の罪滅ぼしをしています。テーカン時代やアトラスの初期は,月に300時間もサービス残業したりとか,会社のベッドで1日4時間寝て,残りの20時間プログラミングをするような生活でしたから。
たまに帰っても,カミさんには『ゲームをやるから,お前は早く寝ろ』と言っていたそうです。自分は記憶にないけど(笑)。それでカミさんから『結婚したのに,独り暮らしと同じ』と責められたり,次の朝出勤するときに,幼い長男から『また来てね』と言われて心を引き裂かれたりね(笑)」
そう言って岡田氏は,この日一番の笑顔を見せてくれた。
“罪滅ぼし”中の岡田氏ではあるが,ゲーム作りから引退したわけではない。現在はとあるプロジェクトに,ディレクター兼オブザーバー的な立場で参画しているという。発表時期は未定だが,岡田氏の原点回帰的なゲームを目指すとのことで,期待が高まるところだ。
“ご近所さん”の関係である筆者と岡田氏だが,今回のように時間をかけて話し込んだのは,おそらく20年ぶりくらいになると思う。あれからお互い年を取ったが,持って回った言い方をせず,思っていることを即座に返してくれる岡田氏の江戸っ子気質は健在だった。「女神転生」「Sword & Poker」と来て,次はどんなものを我々に見せてくれるのか。次なる祭りの幕開けを,楽しみにしたい。
 |
著者紹介:黒川文雄
1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。
現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。
プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設
※参考文献:赤木真澄 著「それはポンから始まった」
- この記事のURL:

















