連載
意外なところにゲーム人 第3回:ゲームの「人を夢中にさせる仕掛け」やログ解析を,進研ゼミの「チャレンジタッチ」に取り入れた島田竜祐氏
 |
かつてナムコやコーエー(いずれも当時)でゲーム開発に携わり,現在はゲーミフィケーションデザイナーとして活躍している岸本好弘氏とともに,ゲーム作りのノウハウをゲーム以外の分野で活用している人を取材していく連載「意外なところにゲーム人」。
今回登場いただくのは,進研ゼミ 小学講座に採用されている「チャレンジタッチ」の開発,および同講座の分析・提案業務を手がけるベネッセの島田竜祐氏だ。島田氏がどのような形でゲーム業界を志し,その後なぜ教育分野へと転進したのか,そして今後何を目指すのかを語ってもらった。
 |
タイトーの体感型ゲーム開発から,ソーシャルゲームの開発へ
島田氏が最初に触れたゲームは,親のPCにインストールされていた「ドアドア」。やがて「ファミリーコンピュータ」がリリースされると,友人とともに「熱血硬派くにおくん」や「三國志」などに熱中していたという。
中学生になるとアーケードゲームの「ストリートファイターII」や「餓狼伝説」などの格闘ゲームにハマり,続く高校時代も友人と一緒にゲームセンターで遊んでいた。
漠然と「ゲームに関わる仕事に就きたい」と考えて大学に進学した島田氏だったが,いざ就職活動を始めると,当時は業務経験のないエンジニアを募集しているゲーム会社がなかったのだという。
「それなら,ほかで業務経験を積んでからゲーム会社に転職をしよう」と考えた島田氏は,当時プログラミングの研修を他社よりも手厚く行っていた企業向けソフトウェアの開発会社に入社した。
そして,自身のスキルに自信が持てるようになった入社5年めごろからゲーム会社への転職活動を開始。翌年タイトーに入社し念願のゲーム業界入りを果たした。
島田氏:
私は「電車でGO!」シリーズが大好きで,タイトーの中途採用面接の前日にもゲームセンターで遊び,エンドロールまで見ていたんです。そのエンドロールにクレジットされていた人が偶然にも面接官で,「昨日もプレイしました!」と話が弾み,緊張することなく面接を終えられたのを覚えています。
岸本氏:
今新卒の就職活動は売り手市場ですが,島田さんの大学時代はちょうど「就職氷河期」と呼ばれる時期で,ゲーム会社におけるエンジニアの求人も業務経験者のみに絞られていたようです。
タイトーでは,「ホッピングロード」や「エレベーターアクションデスパレード」,「超・ちゃぶ台返し!」といった,体感型アーケードゲームの開発を手がけた島田氏。当時は画面上のオブジェクトを動かすだけではなく,自身が思い描いたとおりに筐体が動作することにワクワクしたという。
島田氏:
体感型アーケードゲームの場合,外部の要因で,筐体内の電圧が下がるなど,筐体が想定どおりに動かないケースがたくさんあるんです。それが思いどおりに動いたときは,本当に感動するんです。
また私はソフト担当でしたが,ハード担当のスタッフと協力しないと体感型のゲームは完成しません。そういった「一人ではどうにもできないから人に頼る」「チームで目標を達成する」ようなところもよかったですね。
岸本氏:
今はゲーム開発と言えば,ソフトウェアの開発だけをやっている会社が大半です。一方で体感型アーケードゲームは,ハードの開発者とソフトの開発者が協力しながら一緒に作ります。苦労もありますが,その分喜びも大きいんです。
入社から約2年,会社都合でタイトーを辞めることになった島田氏は,知人のツテでモバイル系のインターネット企業に転職。アーケードゲーム開発から一転,WebアプリやWebサイトの制作,データベースの保守などを担当することになった。
やがて島田氏は,世間でブームとなっていたソーシャルゲームの開発を手がけることに。しかし,「いかにしてお金を稼ぐか」を重視する社内の空気や,当時まだ小学校に上がる前だった島田氏の次男がガチャを回したがる様子に疑問を覚え,「社会的によいとされるものやサービスを提供する仕事に就こう」と考え始めたという。
島田氏:
タイトー時代に作ったゲームは今でも大好きで,お子さんが遊んでいる姿は微笑ましかったですし,自分の子どもにも遊ばせたいと思えます。もし,ずっとタイトーでゲームを作っていたなら,あるいは同じような体感型ゲームを開発できる会社に転職できていたら,教育方面に進もうとは考えなかったかもしれません。
 |
ソーシャルゲームのログ解析を「チャレンジタッチ」に応用
 |
島田氏:
私がソーシャルゲームの開発に携わっていたということに,当時の上司が興味を持って,競合他社のデジタル教材について意見を求めてきたんです。そこで「ユーザーが学習した履歴を確認できて,それが教材設計に生かされている。おそらくどんどん進化していくでしょう」という話をしたところ,それから1か月経ったかどうかという時期に「全社的にデジタル教材に取り組む」ということになりました。「あれ,余計なことをしゃべったかな……」と思った時期もありましたが,今となっては「チャレンジタッチ」を利用している会員はかなり多いですから,結果的によかったんじゃないかと。
岸本氏:
当時はソーシャルゲームブームの真っ只中で各社が激しい競争を繰り広げていました。そこで生まれたノウハウは,他業種ではまだあまり導入されていない,最先端の手法・技術だったということですね。
当時の進研ゼミの課題は,ユーザーである子どもたちが教材をどこまで活用しているか把握できないことだった。また,物心ついたころからスマートフォンなどのデジタルデバイスに囲まれている今の子どもたちには,紙よりもデジタルの教材のほうが向いているかもしれないという見方もできる。
そこで島田氏は「チャレンジタッチ」の開発において,前職のノウハウを生かし,子どもたちの教材活用度を把握するためのログ周りの設計や,メール配信サービスなどを手がけることとなったのである。
ソーシャルゲームでは「登録ユーザーのうち何人がアクティブでゲームをプレイしているのか」「そのうち課金ユーザーはどのくらいいるのか」などのデイリーデータを意思決定に生かせるようチーム内で共有することが一般的に行われている。
それを「チャレンジタッチ」の試みでは,「端末を起動した子どもの数」(ログイン率)と,「その中で提供した教材を完遂した子どもの数」(完遂率)に置き換え,週次のグラフにして確認できるようにしたのである。もちろんその結果は,教材やそのほかのコンテンツの内容にフィードバックされている。
 |
また,そうしたデータをただ追っているだけではあまり意味をなさない。進研ゼミの最終的な理想は「子どもたちの学習継続率を高めること」にあるので,「これ以上ログイン率と完遂率が下がると,継続率が危うくなる」という目標を統計的に設定し,そこに向けてスタッフ各々が努力するという体制が作られた。
さらに島田氏は,ソーシャルゲームの障害発生時などに,特定の会員だけにインセンティブを付与するシステムを応用し,「チャレンジタッチ」のログイン率や完遂率が落ちている子どもたちを特定して励ましのメールを送るシステムも開発。学習をすると遊べるコンテンツや,学習してポイントを貯めると電子辞書や図書券などと交換できるシステムの存在を伝えるようにしているという。
島田氏:
やはりご褒美があると,学習に対しても意欲を見せる子は多いです。もちろん理想を言えば,ご褒美のような外的な動機付けではなく,子どもが自ら学習をしたくなる内的動機付けが望ましいですけれども。
ただ私が子どもの頃と比較すると,小学校受験などが増えているからか,勉強することに対して抵抗感を持つ子どもたちは少なくなっているのかな,と感じます。親御さんが教育熱心だと,自然に学習の習慣が身につくのではないでしょうか。実際,「チャレンジタッチ」のデータを見ても,私が予想していたよりも高い完遂率を示していますし。
岸本氏:
もちろん,学習の習慣づけに一番大事なのは,内的動機です。しかし,何かの理由で学習意欲が低下した子供たちに,楽しい教材を使って学習を始めるきっかけにしてもらう。そして,楽しく繰り返し学習している内に,彼らに内的動機を芽生えさせる……というのがゲーミフィケーションの仕掛けです。
選択の幅を与えた方が子どもは熱中する
現在,島田氏は学習データアナリストという立場で,「チャレンジタッチ」を介して得たユーザーのデータを分析し,コンテンツ制作スタッフに「子どもが夢中になる仕掛け」を提案しているのだが,そこにはタイトー時代に培った「ユーザーを熱中させるゲーム作り」のノウハウが生きているという。
とくにユーザーインタフェースやユーザー体験の部分では,ボタン配置や操作を一般的によく知られているものにするなど,ストレスなくコンテンツを利用できることを重視しているそうだ。
島田氏:
ソーシャルゲームを開発していたときは,ユーザーのアクションに対して5秒以内にレスポンスを返すことを重視していました。そうすることで顧客満足度が高まるので,必要であればサーバー増設やゲームデザイン自体の改修も行っていたんです。
「チャレンジタッチ」では,静止画を使った演出などでレスポンスを速くする工夫をしていますが,それよりもコンテンツを作っているスタッフの思いを優先しています。そもそも進研ゼミには通信教育に関するノウハウが蓄積されており,その中で培われた「子どもが楽しく学べる,夢中になれる表現」がありますから。
岸本氏:
ゲームの素晴らしいのは操作が分かりやすく気持ち良いというユーザビリティを最優先に開発されているところです。ゲームでは当たり前のことですが,皆さんも電化製品のボタンだらけのリモコンに苦戦したり,分かりづらい操作のタッチパネルにイライラしたりした経験があるのではないでしょうか。
そうしたなか,島田氏は子どもたちの学年に応じて演出を変えることを意識している。例えば小学校3年生くらいまでの子どもは「自分が楽しいかどうか」をコンテンツの良し悪しの判断基準にするが,そこから高学年になるに従い「他人との競争・協力」を意識する子どもたちが増えてくるのだという。
そこで低学年向けには,子どもたちの行動に対して何かしらのリアクションがある演出を,高学年向けには他人の存在を感じられるような仕組みを取り入れているとのことだ。
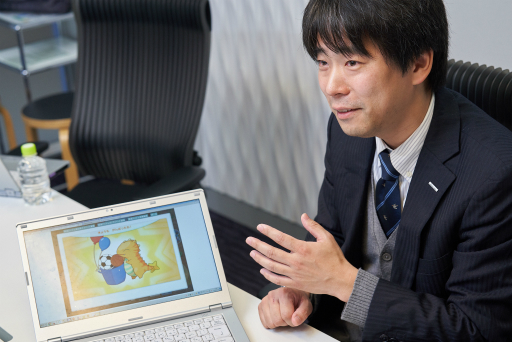 |
また同じコンテンツでも,演出によって子どもたちの満足度が大きく変化するという。例えば隔月で提供しているイベントコンテンツ「ひみつきち」は,子どもが1日1回学習をすると遊べるものだが,人気が高いときとそうでないときの差が大きかった。当初はデータを分析してもアンケートの結果を見ても,なぜその差が生まれるのか開発側もサッパリ分からなかったのだとか。
その後コンテンツごとの仕様を比較したところ,「例え導かれる結果が同じだとしても,子どもに何か選択させたほうが人気が高くなる」ということが判明したそうだ。
島田氏:
例えば,「ボタンを押したら動画が見られる」ではダメなんですよね。「1日1回,恐竜をなでると成長していく」,あるいは「4つのポイントいずれかに豆を置くと,翌日に鬼がそれを食べに来る」といったように,子どもに選択の幅を与えると人気が高くなるんです。今では,イベントアプリのすべてにこういった選択の余地を入れています。
岸本氏:
ユーザーの行動に対してリアクションがあるというのは,すごくゲーム的な考え方です。例えばボタン1つでも,ゲームではない実用アプリだと,機能重視で「ボタンは押せさえすればそれでいい」となりがちなんですよね。
ゲームでは,背景が動くなど常に画面のどこかしらが動いていて,無意識に人の興味を惹くようにしているんですが,ほかの業界の人にはそういう発想があまりないんです。
また似たような事例で,私がよくゲーミフィケーションの講義で取り上げるのが,くら寿司の「ビッくらポン!」です。お寿司を食べて回収口に皿を入れていくと,5皿に1回,景品の当たるゲームをプレイできるんですけれども,重要なのはお客さんが自分の手で皿を投入することなんです。ガチャガチャを回すときにいろいろなジンクスを考えるのと同じで,お客さんは「もしかしたら自分が皿を入れるタイミングで結果が変わるのではないか」と思い熱中していくんです。これが「5皿食べたら自動的にゲームが始まる」という方式だったら,あれほど面白くならなかったでしょう。
子どもたちの多様性や現代人の特性を生かした教材作りを目指す
「チャレンジタッチ」を利用しているのは,進研ゼミのテストで真ん中くらいの成績の子どもが中心だという。その状況を島田氏は,「学習の大切さは分かっているが,せめて楽しく学びたい」と思っている子どもが利用するケースが多いのではないかと分析している。
一方で,2014年4月のスタート時には目新しかった「チャレンジタッチ」に飽き始めている子どもも,最近では散見されるようになったそうだ。
例えば,学習に対する意欲が高いために,見飽きたログイン時の演出やお知らせなどをスキップして,すぐ問題に取り組みたい子どもも少なからずいるとのこと。演出を見たい子どももいれば,そうでない子どももいるという,多様性を認める教材になっていないということを,島田氏は今の「チャレンジタッチ」の課題の1つであると語る。
島田氏:
実はログイン率と完遂率がもっとも高いのは,「チャレンジタッチ」がスタートした2014年度なんです。これは私の見解ですが,2014年度は,5月に「スペシャルコーナー」と「ひみつきち」がオープンし,8月には「SNSコーナー」が開く……といったように,段階的にコンテンツをリリースしていたんです。これは開発スケジュールの都合であり,意図したことではなかったんですが,子どもたちにとっては「エリアが広がっていく」というワクワク感のようなものがあったんじゃないかと。それが2015年以降は,全部のコンテンツがそろっている状態から始まっているので,「いつも同じだな」と感じてしまっているのかもしれません。
「チャレンジタッチ」は教材なので「最初から全部のコンテンツが使えなかったらおかしいだろう」という意見もあるでしょうが,きちんと分析して,段階的にコンテンツをリリースしていく手法なども検討してみたいですね。開発現場にいるとなかなか意見が上層部に伝わらないこともあるんですが,今の私の立場だときちんとデータを示して説得できますから。
もう1つの大きな課題は,学習を始めてから離脱するまでの時間だ。島田氏によると,1つのコンテンツにかかる学習時間が長いほど,子どもの離脱率は高まる傾向にあるという。
岸本氏:
最近は「マイクロラーニング」が注目されています。これは例えば,以前だったら30分連続していた企業研修用の教材動画を5分間に区切って,振り返りのクイズをはさみ,また5分間動画を見せて……を繰り返した方が有効だという考え方です。なぜそんなことをする必要があるかというと,現代の人間にはインターネットやスマートフォンの台頭により,短い時間に集中することに慣れているからです。
おそらく「チャレンジタッチ」も,もっと短い区切りで集中させるようなつくりにしないと,今の子どもに対応できなくなっていくのではないでしょうか。ゲーム的な手法を使い,途中に演出を交えながらスモールステップで学習を進めていくような形が今風といえるかもしれません。
島田氏の今後の目標は,会社としてきちんと意思決定ができるよう,スタッフの誰もが「チャレンジタッチ」のデイリーデータを確認できる仕組みを作ること。また子どもたちが飽きずに学習できる,ひいては自発的に学習したくなるような「チャレンジタッチ」を作り上げていくことだという。
それでは最後に,岸本氏の島田氏に対するコメントと総括を掲載して,本稿の締めとしよう。
岸本氏:
「チャレンジタッチ」のいいところは,画面が動いて子どもたちが楽しく学べることですが,何よりも大事なのは,その子どもたちの動向をログで確認できることです。そこには,ソーシャルゲームが早くから培ってきた,ログ解析のノウハウが生きている。
島田さんは,通信教育で実績のあるベネッセに入社し,ゲーム的な視点と手法を持ち込んだわけです。そこには従来の教育手法のほうが正しいというケースもあるし,ゲーム的な考え方を用いたことで,今まで勉強することに抵抗のあった子どもたちが学習するようになったというケースもあります。これから「チャレンジタッチ」が,子どもたちにとってどれだけ楽しく有益な存在になっていくのか,期待が高まります。
岸本氏の総括
- ソーシャルゲームで使われているログ解析は,他業種でも役立つ
- ゲームのユーザービリティを加えると,通信教育教材は,子供たちのより操作しやすいものになる
- ゲーミフィケーションのポイントは,子どもに選択させること。自分で選んだと思うと楽しさが増す
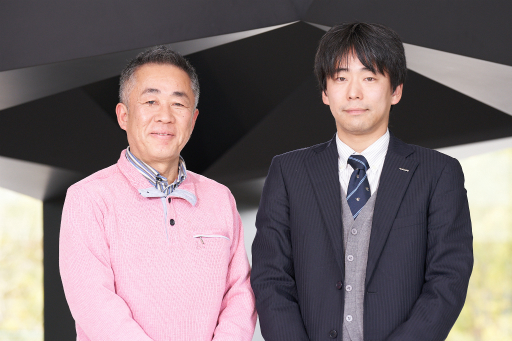 |
- この記事のURL:
















