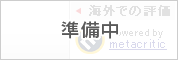イベント
小島秀夫氏と水口哲也氏らがクオリティをどこまで追求するか語ったトークイベント「trialog vol.9」をレポート
 |
trialogは,「What is the future you really want ?(本当に欲しい未来はなんだ?)」を合言葉に,毎回設定される1つのテーマに対して,さまざまな分野で活躍するクリエイターやエンジニア,アーティストなどの三者が,異なる立場から意見を交わすトークイベントである。
第9回となる今回は,「クオリティとミッション」をテーマに,仕事にまつわる2つのセッションが行われた。本稿では,ゲストにゲームクリエイターの小島秀夫氏を招いたセッションを中心に,会場の模様をお伝えしよう。
また,記事の最後には,trialogの共同企画者であるゲームクリエイターの水口哲也氏へのショートインタビューも掲載している。水口氏率いるエンハンスがパブリッシングする「HUMANITY」にも少しだけ言及しているので,興味のある人はご一読を。
セッション「クオリティはどこまで追求するのか」
本セッションは,小島氏と水口氏,そしてtrialog 代表 若林 恵氏の鼎談(ていだん)形式で行われた。
最初の話題は,小島氏と水口氏それぞれから見た互いのいいところについて。水口氏は小島氏を「監督と呼ばれることに集約されている」とし,「自分の中から出てくるイメージをすごく信じており,そこが太くて強い。時間がかかっても自分の思いを成し遂げる」と表現。一方,小島氏は水口氏について,「僕は押されると返すが,水口さんは押したらそのまま引くので,こっちも付いて行ってしまう」とし,「もの作りを仕事にしている点は一緒だが,手法はかなり違う。僕が個体だとすると,水口さんは空気みたいな感じ」と語った。
 |
また2人とも,世代が近いので好きな音楽やアートが同じだったりと似たものに影響を受けているという。小島氏は「2人ともアート系」だとし,今は違うと前置きして「僕らがゲーム業界に入った当時,ハードやソフトを扱う理系の人達は,アーティストに対するリスペクトがあまりなかった」と話すと,水口氏も「ずっとフラストレーションを溜めながらもの作りを続けている数少ない仲間同士」と同意した。
さらに水口氏は「ゲームはテクノロジーの進化とともに表現力を上げてきた体験のメディア。昔は妄想を膨らませても実現できる部分は少なかったが,テクノロジーの進化で少しずつ実現できる部分が増えていった」とし,「そうやって『DEATH STRANDING』が完成したときは,小島さんが今まで以上に溜まっていたものを吐き出せたんじゃないかと,自分のことのように感じた」と話していた。
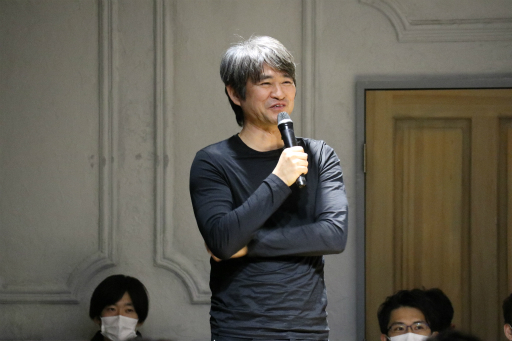 |
「DEATH STRANDING」における一番のチャレンジを問われた小島氏は「ハードやプラットフォームは変わったが,作っているのはこれまでと同じゲームなので,その意味ではあまり苦労はない」としつつ,「ゼロから事務所を借りて,室内の装飾をどうするかを考えたり,スタッフの面接をしたり,銀行に行ったりするのと並行してゲームの企画を考えることは新しい体験だった」と回答。
また自身のスタイルについて,「もの作りについて常に考えていて,その結果として商品になり収益につながる。それが逆になったことはない」とし,「今回は,幸か不幸かどれだけ儲けるかを考えなくて良かったので,自分の作りたいものを,一緒に作りたいという人を集めて作ることができた」と語った。
また「DEATH STRANDING」でようやく実現できたことは,「俳優を使うこと」だったという。主要キャラクターのみならず登場人物全員にリアルのモデルがいるとのことで,小島氏は「フォトリアルのゲームは全部同じ。モデルそのままでなく,データ化した身体のパーツを組み合わせて1人の人物を作ることもある。そうしないとリアルにならない」と説明。さらに「実はカニも最初はデザイナーに作ってもらったが,左右対称でリアルに見えなかったので,リアルのカニをスキャンして作り直した」と開発中のエピソードを披露した。
独立してから予算やスケジュールに対する考え方が変わったかどうかという問いには,「それは変わらない。予算とスケジュールがないと,もの作りはできない」と小島氏。自身が完璧主義者であり,放っておくとずっと手直しを続けてしまうとして,「スケジュールがあるからこそ,そこまでにできることを全力でやる。すべてのクオリティを上げるのは無理なので,優先順位を付ける」と語った。
また水口氏が「僕らは時間さえあればずっと作り続けてしまう。完成させたくないという病気」と表現すると,小島氏も「完成させたら,明日からどうしようと思ってしまう。あんなに楽しい玩具だったのに,もう遊べなくなる」と同意していた。
さらに水口氏は,エンターテイメントにはおおよその時間枠が決まっていることに言及。例えばテレビドラマシリーズだったら1回あたり45分程度,映画だったら1本あたり長くても2時間40分程度だが,ゲームにはそうした枠がない。しかもゲームは体験を提供するものなので,どこまでも作っていけるというわけである。
そのため小島氏はゲームを企画するとき,最初に枠を決めるとのことで,「ビジュアル,サウンド,ストーリー,ゲーム性のバランスをまず決める。そして予算とスケジュールを見ながら,日々調整していく」「ゲームはテクノロジーに依存しているので,開発中は毎分毎秒と言っていいくらい問題が起きる。それらを放置しておくと作り直しとなり時間の無駄になるので,その都度調整する必要がある」と語った。また最初にPVを制作するのは,ビジュアルやサウンドなどをどのくらいのレベルで作るか,ひいては人月の目安を示すためであるとも説明していた。
一方,水口氏はゲームの開発初期にコンセプトを周囲に伝えるため,詩を書くことがあるという。最初に微細な部分までイメージしてから削ぎ落としていくと詩のようになるので,それを周囲に読ませてどう感じるかを尋ねるとのことで,「最初のイメージとあっている答えはほとんどない。でも会話のキャッチボールを通じて,イメージを共有していく。小島さんとは正反対のやり方」と語った。
 |
小島氏は,ゲームの企画を考え始める当初はストーリーや設定,世界観などをバラバラに作っていくという。それが日々の方向修正を重ねていくうちに,パズルのようにすべてが綺麗にハマる瞬間があり,それが気持ちいいのだそうだ。
ただ,そうやって1人ですべてをコントロールする手法は小島氏の独特のものであり,水口氏は上記のようにまた別の手法を採っている。その理由を両氏はゲーム開発について教えてくれる存在がいなかったとし,小島氏は「会社は何かを教えるところではないと言われて驚いたが,よくよく聞いてみたら誰もゲームの作り方を知らなかった」というエピソードを披露。「今は『ゲームオーバーや復帰ポイントはこうあるべき』といったようなフォーマットがあるが,僕らの頃は何を作っても良かった」「インディーズを見ても,今はある程度のフォーマットに沿ったものが多い」と続けた。
話題はゲームのジャンルにもおよび,小島氏が昔はジャンルなんて考えずに作っていたと語ると,水口氏はマーケティング担当に「このゲームは,どのジャンルの棚に置けばいいのか」と問われたエピソードを披露。だからと言って現在が窮屈だというわけでもなく,小島氏は「フォーマットの中で売れるものを作るということも,クリエイターとしてのチャレンジ。ただ,そうでないチャレンジもあるのに今は塞がれている感がある」「『DEATH STRANDING』では,こういう発想もあり,さらにそれをビジネスとして成立させるということを見せたかった。」と語った。
「DEATH STRANDING」は賛否が大きく分かれるゲームだが,小島氏は「新しいものには必ず賛否がある」とし,想定内のことだったとする。また自分の作ったゲームに対する否定的な意見をどう捉えているかという質問に,水口氏は「見るとヘコむので見ないようにしている」と回答。
さらに意外な反応があったか問われた小島氏は,「最低限の必要なミッションをこなしてなるべくストーリーに集中してもらえるよう作ったつもりが,ずっと道路を作っていたり配達したりしている人がものすごく多い。嬉しい誤算」と話していた。
またそうやって予想外の遊び方を続ける人達がいる理由について小島氏は,「最初は自分で使うために橋を架けたり,ロープを垂らしたりする。でもあるとき,その橋やロープが誰かの役に立っていることに気づく。そういう体験をすると,次は他人のことを考えて何かするようになる。その報酬が『いいね!』だけというのは賭けだったが,うまくいった」と説明。スタッフに反対されても,「それにつながるよう設定やストーリー,キャラクターを作っているので,そこを曲げるならやらないほうがいい」と貫き通したエピソードを語った。
さらに多くのゲームではA地点からB地点に行くために最短のルートを模索することになるが,「DEATH STRANDING」では風景を楽しめるよう作ったこともリスクになっていたとし,「すでにあるものを作るのであれば,僕の出番はない。そうなったら引退」と話していた。
そうした話を受けて,水口氏は小島氏のゲームによるストーリーテリングが世界中の人達に影響を与える存在となっていることに言及。小島氏は「面白いと思ってもらえる,時間を忘れるほど楽しんでもらえることは重要。でもそこで完結してほしくない。ゲームの中で体験したことを現実世界に持ってきて,考え方や振る舞いが変わるなど何かプラスの変化があってほしい。なぜかと言うと,僕は本や映画からそういう影響を受けたから」「本や映画,ゲームではリアルには体験できないことも体験できる。そういった体験も人格に影響を与えると考えている」と語った。
 |
さらに水口氏は,両氏がストーリーテリングをする手法として本や映画を選ばなかった理由として,30数年前のゲームが持っていた世界中に拡散するパワーを指摘。当時のゲームはビジュアルもサウンドも現在とは比較にならないくらい表現力に乏しかったが,逆に日本語など特定の言語を使えなかったからこそ世界中に広がったというわけで,両氏はその魅力に惹かれたのである。
水口氏は「今のゲームは表現力が伴ってすごい状況になっており,さらにその先が見える。昔はやりたいことがあっても,限定的にしか実現できなかったけれど,30年間やり続けてきた結果,小島さんは『DEATH STRANDING』を作った」「僕は僕で音のクオリティが格段に上がったので,それを体験に組み合わせて音楽を演奏しているかのような気持ちよさを作り出せるようになった。テクノロジーの進化によって解像度が上がり,感動の質が上がる。こんな差分はゲーム以外のメディアにはない」と話していた。
一方,小島氏は自身がMSX用のゲームを作っていた頃,水口氏が作っていたようなアーケードゲームにはビジュアル面で勝負にならず,ストーリーや世界観で勝負するしかなかったとし,「今振り返るとそれが良かった。もしアーケードゲームを作っていたら,ストーリーを評価されることはなかったかもしれない」と語った。
世界を対象にするということは,さまざまな国や地域の文化や宗教を考慮に入れてストーリーを考える必要があるのではないかと問われた小島氏は,答えになるかどうか分からないと前置きして「これまで読んできた本はほとんどが翻訳もので,映画も洋画ばかり観てきた。また子どもの頃から小説を書いているが,日本を舞台にしたことはほぼない。ゲームもアメリカや宇宙を舞台にしているが,作りたいものを無理なく作っている」と回答。とは言っても作っている中で,全世界共通で受け入れられる家族・血縁の物語やバイオレンスなどを意識することはあるという。
また民間軍事会社(PMC)や無人兵器などはリアル世界で台頭する前に,小島氏のゲームに登場したが,氏自身は「それは突飛なことではなく,明日のこと,2日後のことといったように地続きに考えていく中に少し仮想のことを入れているだけ。このまま行くと,こういう世界になるということを書いている。それが現実化してしまうのは,クリエイターとして悔しい」と説明した。
そうした情報をどうやって取捨選択しているのかという問いには,「本屋に行くというのも1つの手段。今はネットで多くの情報を得られるが,本屋に行くと雑誌の表紙を見るだけでも世間で何が流行っているかが分かる」「また本屋には何万冊も本があるけれども,その中で面白いのはせいぜい100冊くらい。ランキングで選ぶのも悪くないが,自分のセンスで面白いものを選び出す下地作りのために本屋に通っている」と回答。「それは映画も人も同じ。いい人にめぐり会うチャンスはなかなかないが,それは運と言うよりもセンス。ネットは便利だけど,それだけではセンスは磨かれない」と持論を示した。
 |
セッションの終盤には,来場者や配信の視聴者からの質問に小島氏らが回答するコーナーも設けられた。「これからを生きる若者に必要な資質とは何か」という質問には,小島氏が上記の発言を踏まえ「自分のセンス。自分を信じるしかない」と回答。とくにAIが台頭する世の中ではセンスが重要になるとした。
また水口氏は「もっと世界に出たほうがいい」とし,「よく日本や日本人はこうあるべきという議論を見かけるが,実際に海外でに何人かを問われることは少ない。もっと自分自身のアイデンティティと向き合うことになるので,若いうちに体験しておいたほうがいい」と語った。
「選択を迫られたときに何を軸にするか」という質問には,小島氏がここでも「自分を信じるほかない」と回答。また自分が作りたいものがある場合は,自分がプロデューサーまで務めて予算管理まで含めて全部自分でやったほうがいいとも語った。また水口氏も,人任せにすると思うようにいかなかったときに自分に返ってくるダメージが大きいので,ある程度自分でできるようにしておいたほうがいいと話していた。
「いい仕事をするために,どんな自分でありたいか」という質問には,小島氏が「自分が死んでも人の記憶に残ること」と回答。また水口氏は「好きなことをやって生きていけて,それが周囲にいい影響を与えることが理想」とし,「シンプルで難しいが,それがいい仕事」と話していた。
 |
水口哲也氏ショートインタビュー
4Gamer:
まずは小島氏とのセッションについて,率直な感想をお願いします。
水口哲也氏(以下,水口氏):
小島さんとは本当に仕事のやり方やスタイルが全然違うんだけど,時代の中で影響を受けたものや見てきたものが近いので,いつも不思議な方だと思っています。「DEATH STRANDING」では,クリエイターとしていろんなものに挑戦したと思うんですよ。例えばインディペンデントになった,あるいは今までのものを捨ててまったく新しいものを作る。人としても会社としても素晴らしい。そんなことをトークしながら改めて考えていました。僕もできるだけ長くゲームを作り続けたいので,20年後にまたああいった話ができるといいですね。
4Gamer:
「DEATH STRANDING」をプレイしてみていかがでしたか。
水口氏:
まだエンディングまでたどり着けていないんですが,ゲームを始めてから自由に操作できるようになって2時間くらいでいろんなものが分かってきました。小島さんの静かな闘志やゲームに込めたメッセージ性,今まで彼が示してきたいろんな断片が,今までとは全然違う形で結実したのかと。……本当に大変だったと思いますよ。それをああいう良いゲームとして世に送り出したのは,さすがですね。これからも小島さんはますます進化していくんじゃないかと感じました。
4Gamer:
今日のセッションの中で,「時間があったら,ずっと手直しを続けてしまう」といったクリエイターの業のような話がありましたよね。一方で水口さんも小島氏もクリエイターであり,会社の代表でもあるという立場ですが,どうやってクリエイティブとビジネスの折り合いを付けているのでしょうか。
水口氏:
制約がないとどこまでも作ってしまうので,そのために目標や締切を設定している側面は確かにあります。自分1人ではなく,チームや周囲の人を巻き込んでいろんな責任を負っていますからね。もし予算を気にしないでいいくらい大成功したら,延々作り続けて納得するまで世に出さないゲームが出てくるかもしれない。
その一方で,次に行くために今作っているものを終わらせるという面もあります。やっぱりいくつになっても成長・進化し続けたいですから。そのために目標や締切を設定しています。
4Gamer:
そのほか今日のセッションの中で,何か気づいたことはありますか。
水口氏:
小島さんは変わらないなと。それは多分僕も同じで,進化はしているんですけれど,本質は変わらない。それを確認できました。
4Gamer:
最後に,エンハンスからパブリッシングされる「HUMANITY」について,注目している人に向けてメッセージをお願いできますか。
水口氏:
中村勇吾さん率いるthaが本気になって作っていて,エンハンスも本気でバックアップしています。ゲームとして,体験として「なるほど」と言ってもらえるものを世に送り届けたいと思って鋭意開発しています。本当に良いものができるまで出したくないと思っているので,具体的にいつとはまだ言えないのですが,なるべく早く発売日をお伝えしたいと考えています。
4Gamer:
期待しています。ありがとうございました。
 |
- 関連タイトル:
 DEATH STRANDING
DEATH STRANDING
- この記事のURL:
キーワード
- PS4:DEATH STRANDING
- PS4
- アクション
- CERO D:17歳以上対象
- Sony Interactive Entertainment
- コジマプロダクション
- ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- イベント
- インタビュー
- ライター:大陸新秩序
(C)2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.