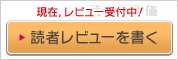インタビュー
「LEFT ALIVE」はローグライクのようなゲームを目指したサバイバルアクション。ディレクターの鍋島俊文氏にインタビュー
ロボットシミュレーション「フロントミッション」シリーズの流れを汲む作品のディレクターを,「アーマード・コア」シリーズで知られる鍋島俊文氏が務めるということで,発表時から話題を呼んだ。しかし,蓋を開けてみれば,実際は生身の人間がメインとなる“死にゲー”で,数少ないアイテムをやりくりしながら進んでいくシビアなタイトルだった。
 |
もちろん,プレイレポートでお伝えしたとおり,本作には本作ならではの魅力がある。今回4Gamerでは,これがどういったところから始まったのか,フロム・ソフトウェアからスクウェア・エニックスへ移った鍋島氏が開発に携わった経緯はどういったものかなどを,鍋島氏に聞いてみた。
 |
スクウェア・エニックスでの新たなチャレンジ
4Gamer:
よろしくお願いします。鍋島さんがいつの間にかスクウェア・エニックスに移っていて,表に名前が出てきたのはLEFT ALIVEが発表されたタイミングだったと思いますが,まずは本作の企画が動き始めたいきさつを教えてください。
 |
企画のきっかけは,フロントミッションの生みの親の一人である橋本(真司氏)から,もう一度シリーズをしっかり展開したいという話を聞いたことから始まっています。
4Gamer:
フロントミッションの世界観で,しかも鍋島さんが関わるとなれば,当然ロボットゲームかと思った人も多いのではないかと思うんです。実際,我々も発表時のトレイラーからそう思っていましたし……。予想とだいぶ違ったものになっていて驚きました。
鍋島氏:
そうした期待をされた方が多いと思いますので,本作の内容について誤解を与えないようにしたいとは思っています。
長らくロボットものを作っているからでしょうか,いろいろなインタビューで「鍋島さんといえば,ロボットゲームですが……」と切り出されることが多いんです(笑)。そう言われると申し訳ないんですが,僕自身すごくロボットものを作りたくてゲーム業界に入ったというわけではなくて,入社して最初に参加したのが初代の「アーマード・コア」で,そのままシリーズに継続して関わったというのが本当のところです。自分としては遊びとしてのゲームだったり,そのシステムを作る部分をやりたくて,そのテーマになっていたのがロボットだったということになります。
4Gamer:
ロボットありきでゲームを作ってきたのではなく,ゲームシステムや遊びを作っていくうえでの題材としてロボットがあったというわけですね。
鍋島氏:
フロム・ソフトウェアという会社自体が,どちらかというとそういう会社なんだと思います。
4Gamer:
とはいえ,LEFT ALIVEに関してはフロントミッションという土台がありますから,そういうわけにはいかないですよね。鍋島さんは,フロントミッションをどういったものとして捉えて本作の開発を進めたのでしょう。
鍋島氏:
僕はフロントミッションを,ロボットものというより,戦争ものとして捉えています。主人公という個人から見た戦争を描くのがフロントミッションらしさではないかと。
4Gamer:
シリーズは一貫して,戦争の中で抗う人間の姿を描いていますね。
鍋島氏:
ロボットものというくくりで語られがちなんですが,シリーズの特徴としてかなり設定やストーリー,キャラクターを重視しているものでもあります。そこは大事にしようと思いました。そうした中で,戦争におけるどの側面を切り取るのかと考えていったところで,「サバイバル」というテーマが出てきました。
4Gamer:
サバイバルを描くのであれば,ヴァンツァーに戦術を指示するよりも,人間を操作する方が良いと。
鍋島氏:
そうです。自分でヴァンツァーを所有していることと,サバイバルというテーマは相容れないところがありますから。シミュレーションゲームにすることも考えたんですが,僕はずっとアクションゲームを作ってきた人間ですから,自分の得意なところで勝負しようと思いました。その結果が,戦争の中で人間があがくサバイバルアクションのLEFT ALIVEなんです。
4Gamer:
タイトルに「フロントミッション」という単語が入っていないのはなぜでしょう?
鍋島氏:
そこはかなり検討したのですが,従来作通りのシミュレーションと勘違いされてしまうため,使用しないことになりました。
僕はゲームのタイトルを決めるのが苦手なので結構難航しました。海外から「ALIVE」という案が出てきて,そこからLEFT ALIVEのタイトルを決めています。単に生きているのではなく,何かの力に生かされている。生きた状態で放置されているというニュアンスが作品にピッタリですし。
 |
プレイの自由度とリソース管理がテーマ
4Gamer:
ジャンルをサバイバルアクションに決めた後,どういったタイトルを目指して開発を進めてきたのでしょうか
鍋島氏:
僕はスタッフに「ローグライクのようなゲームを作りたい」と説明していました。
 |
4Gamer:
そこでローグライクゲームが出てくるのが意外なのですが,どういうことでしょう?
鍋島氏:
LEFT ALIVEでは,「目的を達成するための手段の多様性」と「リソースの管理と消費」をテーマにしているんです。
ローグライクゲームにおいて,ダンジョンでの目標は“階段にたどり着く”ことであり,途中のモンスターは倒しても無視しても構いません。状況によっては戦わないことが賢明な場合もあります。その道中で,武器や食料といったリソースを集めていく。そして,どうしても戦わなければならないモンスターハウスのようなところで,溜めたリソースをつぎ込んで一気に勝負をかけるわけです。
4Gamer:
なるほど。そう言われると,本作のプレイ感そのままですね。モンスターならぬ敵兵士を避けたり戦ったりしつつ,銃弾や薬といったアイテムを溜めていく。そして,チャプターの最後では戦いが避けられませんから,少しでも有利になるようにあらゆるアイテムを使っていくと。
ただ,本作の場合,“階段にたどり着く”のが大変ですよね。プレイしてみて,思った以上に難度が高くて驚きました。ちょっとミスしただけで本当に容赦なく殺されますし,弾薬や回復薬のリソースも限られているじゃないですか。
鍋島氏:
僕がゲームを作ると気づいたら難しくなっているというのもあるんですが。とくに最初のステージは,ゲームのコンセプトを理解してもらうため,できるだけ早い段階で1回ゲームオーバーになってもらう考えで作りました。
4Gamer:
見事に開始直後に殺されました。
鍋島氏:
早く死んでもらう理由としては,「敵と積極的に戦うゲームである」という誤解を解いておきたかったんです。社内の人間にもテストプレイしてもらったんですが,ゲーム慣れしている人ほど先入観があり「はいはい,いわゆるTPSなのね」と敵兵士にヘッドショットを決めようとするんですよ。本作は策もなくフラフラと敵の前に出て行って何とかなるゲームではないですし,そもそも普通,フル装備の兵士にハンドガン一丁で挑んだりしませんよね(笑)。
4Gamer:
確かに(笑)。
鍋島氏:
もちろん,難度を下げて作ることもできたのですが,そうするとTPSのうまい人はシューティングのテクニックだけを使い,サバイバルという面白いところを味わえないままクリアしてしまいます。それでは「平凡なTPSだよね」という感想しか抱いてもらえません。
4Gamer:
ステルスキル(背後から忍び寄っての一撃必殺)がないのも同じ理由でしょうか。
 |
そうです。ステルスキルを導入するか否かは,開発内でも議論がありました。しかし,なまじステルスキルがあると,うまい人なら敵兵全員をこっそり始末できてしまいます。
本作はTPSでもステルスでもなく,あくまでサバイバルアクションです。生き残ることが目的ですから,そのためには逃げるなり戦うなり,手段も道筋もプレイヤーが選ぶことになります。
実際にいろいろな人にテストプレイしてもらいましたが,進め方に差が出て面白いですね。慎重に敵を観察してから見つからずに進む人もいれば,敵を後ろから金属パイプで殴りつけ,ダウンしているうちに駆け抜ける人もいて,千差万別です。そして皆さん「これが正解ですよね!」っていうんです(笑)。
4Gamer:
殴って逃げるっていう発想がもう面白いんですが,そのあたりはステルスに慣れていない人ほど,意外なプレイをしそうですね。
本作では生存者が出てきますが,彼らを助けたところで,アイテムをもらえるなどのメリットがほとんどないのもリアルに感じました。
鍋島氏:
開発チーム内で議論はありましたが,助けると何かもらえるという形にしてしまうと,それを踏まえたバランスにしないといけない部分が出てきて,助けることが義務になってしまいます。それを避けたかったんです。
それからこれは自分のこだわりなんですが,僕は人助けでメリットがあるというのはあまりやりたくありませんでした。ギリギリの状況の中,メリットもないのに人助けをするのがいいんじゃないかと。最終的には,生存者本人からアイテムをもらえるわけではないけれど,近くにアイテムが落ちていることもあるという,折衷案を採用していますが。
4Gamer:
生存者と接するのも,一筋縄でいかないのがスリリングでした。民間人と話す際も選択肢を間違えると絶望して自殺してしまったり,戦意旺盛な兵士に弾薬や薬を渡すとそのまま無謀な戦いに挑んで戦死してしまったり。自分の選択で他人が死に向かっていくのが,ちょっと怖かったです。
鍋島氏:
ゲームに慣れていると,いわゆるテンプレ的な正解が分かってしまうというのがイヤだったんです。生存者の描き方は,自分が昔好きだった「セプテントリオン」(※)というゲームをオマージュしているところがあります。
※「セプテントリオン」
1993年に発売された,スーパーファミコン用アクションアドベンチャー。沈没寸前の豪華客船で,生存者を救いながら脱出を目指す。
4Gamer:
「極限状態でのサバイバル」「生存者を救うか否かは選択次第で,簡単に救うことはできない」と,セプテントリオンとの共通点は多いですね。オマージュと聞いて納得がいきました。
鍋島氏:
個性的な人がたくさん出てくるゲームでしたね。「この船はどうせ沈んじまうんだ!」とヤケを起こして酒をガンガン飲んでいる人がいるなど,極限状態で人間性が露わになるところが面白いんです。LEFT ALIVEでも,キャラクターをゲームのコマにしたくなかったので,生存者にはちゃんとバックボーンが設定されています。
4Gamer:
キャラクターについても聞かせてください。プレイしてみて,LEFT ALIVEは戦場における人間ドラマに注力しているという印象を受けましたが。
鍋島氏:
プロットを作った際,ちゃんとフロントミッションとして受け入れられるお話になっているかどうかが気がかりだったのですが,シリーズすべてに関わっているスタッフから太鼓判を押してもらえたので,安心しています。
4Gamer:
今回は複数の主人公が出てくる話になっていますよね。
鍋島氏:
複数主人公の物語がひとつにつながっていくのは「フロントミッション4」以来の試みになっています。ヒーローの物語ではなく,あくまで「普通の人が戦場で苦労して生き抜いていく」話だったので,どこかにいそうな人物像を描きたかったんです。そこで,年長者(レオニード)と若者(ミハイル),そして女性(オリガ)の3人を出そうということになりました。
4Gamer:
最初にプレイするキャラクターということもあって,ミハイルの未熟さが印象的でした。軍人なのにどこか平和ボケしていて,民間人を守るという職業意識も薄いですし,敵から襲撃された際に「戦争が起こるなんて聞いていなかった」と隊長に文句をいうシーンもあって。
鍋島氏:
僕も,個人的にはミハイルが好きですね。これまでに作ってきたゲームにはいなかったタイプのキャラクターですし。
LEFT ALIVEには,戦場に取り残された生存者がいますが,主人公達は彼らを助けるか否かという選択をしなければなりません。軍人として未熟であるがゆえに「助けない」選択ができるのがミハイルであり,その際の展開も成熟した軍人としての側面を持つレオニードやオリガより面白くできますし,プレイヤーさんの心境ともシンクロするんです。
サバイバルの主人公としてなら,弱い人間である方がふさわしいですしね。
4Gamer:
キャラクターデザインについて何か苦労はありましたか?
鍋島氏:
レオニードとオリガは最初のラフからそう変化していません。一番難航したのがミハイルですね。血まみれ,泥まみれになりつつも生き抜いていくという本作の雰囲気を表現した上で,イケメンかつ,未完成の軍人でなければならない。キザな感じから正統派主人公的なルックスまで,いろいろなイメージを考えて完成しました。
4Gamer:
ステレオタイプなキャラクターでないからこその苦労があったんですね。
 |
リアリティのために,ロシアの下水道まで取材した
4Gamer:
本作は黒海沿岸が舞台になっていますが,開発するに当たって現地を取材されましたか?
 |
はい。3年ほど前にロシアへ行きました。取材の成果が現れているのは,主に街並みや下水道の中といった風景の部分ですね。
4Gamer:
ゲーム中の下水道は迷路のようになっていますが,ロシアの下水道もああいった感じなんでしょうか。
鍋島氏:
そうですね。実際にガイドさんに下水道を案内してもらったんですが,ロシアの下水道は建て増しを繰り返しているので,帝政ロシアに作られたレンガの区画が,そのままソ連時代のコンクリートのエリアに繋がっていたりするんですよ。
4Gamer:
ロシアの歴史がそのまま現れている感がありますね。
鍋島氏:
下水道の中には,ソファーが置かれている一角もありました。地元の不良がアジトのようにしていて,パーティーなどをするそうなんです。ワインの瓶なんかが転がっていたりもして。
4Gamer:
下水道がたまり場になっているみたいなシーンって,ゲームでもよく見ますけど,本当にあるんですね。
ところで,本作の言語は英語ですよね。ロシア語にしなかったのはなぜでしょう。
鍋島氏:
そこは自分としても非常にやりたかったところだったんですが,音声ということになるとローカライズやこちらでの演技のディレクションが難しいので,やむなく断念しました。
現地に行ったとき,ゲームショップの店員さんに話を聞いたのですが,ロシア語が入っていても,現地(ロシア)で評判がいいとは限らないみたいなんですね。ロシアでこういう声の仕事に関わっている方が,あまり多くないようなことは聞きました。「演技のレベルが高くないと感情移入が削がれてしまう。だから,ロシア語の吹き替えがあっても英語音声+ロシア語字幕でプレイする」と言っていたぐらいで。
4Gamer:
ああ……海外ゲームで変な日本語が流れてくると微妙な印象になりますし,気持ちは分かります。
スクウェア・エニックスらしからぬゲームを作るというミッション
4Gamer:
難度の高いLEFT ALIVEですが,これからゲームを始める人向けにオススメのアイテムを教えてください。
鍋島氏:
ドローンの残骸から手に入る「感知センサー」と,いろいろな場所に落ちている「携帯端末」を組み合わせて作る「索敵センサー」ですね。敵の動きが壁越しに分かる重要アイテムなので,素材も手に入りやすくしています。
4Gamer:
適当に突っ込んでいくと,本当にあっさり死にますからね……索敵のためにアイテムをケチって酷い目に会いました。
鍋島氏:
あとは「ウォッカ」と「布」で作る「火炎瓶」もオススメですね。ちなみに,アイテムの中には「スモークグレネード」と「発煙瓶」,「フラググレネード」と「爆発缶」のように効果が似ているものもあるんですが,性能面で差別化しています。具体的には,発煙瓶や爆発缶のようにクラフトで作るものの方が発動は早いけれど,効果範囲は狭いんです。敵兵にはAIが設定されていて,「近くに物が落ちた時に認知できるかどうか」を確率で判定し,その後「行動に移るまでの時間」もランダムなので,うまく使い分けてもらえると嬉しいです。
 |
4Gamer:
周回プレイ的なやりこみ要素はあるんでしょうか。
鍋島氏:
1回プレイしただけではストーリーの全容が掴めないと思います。ただ,どんなエンディングでもゲームをクリアすれば「NEW GAME PLUS」という機能が使えるようになります。プレイの仕方によってポイントが貯まるようになっていて,「NEW GAME PLUS」では,それによって得たポイントを消費することで,体力やスタミナを上げることができます。
4Gamer:
1周目ではクリアできなかったところも,キャラクターを強化すれば何とかなるかもしれませんね。ではフロントミッションシリーズのファンに向けたサービスはありますか?
鍋島氏:
ステージ内に置かれている「アーカイブ」には世界観関連の資料が書かれています。キャラクターのプロフィールもしっかりと読み込んでいくことで,「もしかするとこのキャラクターは,過去作のこの戦いに参加していたのではないか」ということが類推できたりもしますので,ファンの方はぜひアーカイブを揃えてみてください。
また,ヴァンツァーを所有することはできませんが,特定のステージでは敵の機体を使えますし,ヴァンツァーに乗った状態で最初から最後までプレイするチャプターもあります。普段が苦しいぶん,ヴァンツァーに乗れるところはストレス発散できるようなバランスにしていますので,楽しんでいただけるのではないでしょうか。
 |
4Gamer:
それでは最後に,発売を楽しみにしている人にメッセージをお願いします。
鍋島氏:
比較的自由度の高いゲームなので,いろいろな方法を試してほしいです。目的は生き延びることですから,どんなに泥臭くても,かっこ悪くても,華麗なプレイにならなくても,クリアできればそれが正解です。
例えやられてしまっても,これまでと違ったアイテムやコースを試すと案外スルっと抜けられたりもします。そもそも,動きがパターン化しないようなAIになっていて,同じプレイをしても事故が起きますから。オススメは,誰かほかの人と一緒にプレイすることですね。自分では気付かなかったところに気づいたりもしますよ。
4Gamer:
難度にしても,TPSともステルスアクションとも違うバランスにしても,何というかスクウェア・エニックスさんらしくない,独特のゲームですよね。
鍋島氏:
「ドラゴンクエスト」や「キングダムハーツ」のようなものと比べると,もちろんコア向けだとは思います。ただ,そういうものを作っていくのが,僕のミッションなんじゃないかなとも思っています。
4Gamer:
発売を楽しみにしています。本日はありがとうございました。
 |
- 関連タイトル:
 LEFT ALIVE
LEFT ALIVE
- 関連タイトル:
 LEFT ALIVE
LEFT ALIVE
- この記事のURL:
(C)2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: YOJI SHINKAWA (KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.)
(C)2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: YOJI SHINKAWA (KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.)